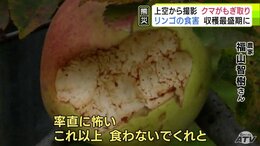「警笛鳴らせの標識」どんな場所にある?鳴らす長さと頻度は?
例えば、警笛鳴らせの標識がある場面。実際、この標識は、見通しの悪い山道のカーブなど、出会い頭の事故が起きやすい場所に設置されています。

具体例として、愛媛県大島にあるカレイ山展望台に至る道路では、警笛鳴らせの標識がありますが、この警笛鳴らせの標識は、区間の始まりなどを示す「⇒」や「⇔」の補助標識とともに設置されています。

ところで、クラクションやベルは、どのくらいの長さ・頻度で鳴らさなければならないのでしょうか?
愛媛県警交通企画課によりますと、まず、警音器鳴らせについて区間の指定があるときは、「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の曲がりかど、見とおしのきかない上り坂の頂上」を通行する車両には、全て警音器を鳴らす義務があるとされています。
ただ、「どの程度の長さや頻度について、通行時における道路状況、天候等によっても異なるため、一律の解釈はできず、個別に判断する」と説明があり、車でも自転車でも同様の解釈とのことでした。
そもそも道路交通法では、クラクションやベルの使用を「危険を防止するためやむを得ないとき」などに限定しています。そのため、画一的な基準はなく、その場の危険を知らせるのに必要十分で、常識的な範囲の合図を各自が判断することが求められます。