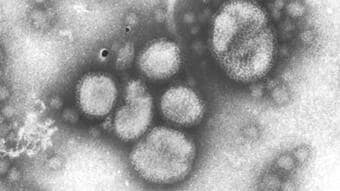15日、小泉農水大臣が就任後初めて福島県内を視察し、地元のコメ農家などと意見を交わしました。
大臣は「コメの価格高騰を抑えていく」と改めて政策への理解を求めました。
震災・原発事故後の県内の農林水産業の現状を視察に訪れた小泉農水大臣。
県内各地をまわる中、生産者に訴えたのはコメの価格高騰に対する農業政策への理解でした。
【小泉農水大臣】
「あまりにコメが高くて、高い関税を払ってでも海外から直接輸入するという民間事業者が増えているということです。1年間で2倍、2・5倍揚がっている価格高騰はやはり高過ぎますから、ここの部分を抑えていくことによって消費者の方のコメ離れを防がなければならない」
一方、コメ価格高騰の原因究明を求める声も。
【県農業協同組合中央会・管野啓二会長】
「根本的に今回のコメ不足は何だったのかというのを、やっぱりはっきりと解明してほしいというのがありますので」
【小泉農水大臣】
「皆さんの感覚からすると、そんな農水省が言うほど生産量ないよと、収穫量ないよと言うのが感覚なんです。その声は相当各地域から届いているので。みなさんが、ああようやく現場の感覚に近づいてきた、そう思ってもらえるようにします」
その後、二本松市や福島市を訪れた小泉大臣は、改めて生産者に「コメの価格高騰を抑え消費者と生産者の思いを一致させていく」と、農業政策への理解を求めました。
県内の視察を終えた小泉大臣は・・・
【小泉農水大臣】
「現場で農水省が出しているものと実感が全然違うと、やはりこういう政策の基盤となるデータ統計の信頼を回復しないことには、中長期のコメ政策というのは立案できない」
そして16日、小泉大臣は統計データの見直しについて次のように述べました。
【小泉農水大臣】
「約70年前から毎年秋に実施してきたコメの作況指数の公表を廃止することにいたしました。作況指数の算出に使っている過去30年のトレンドを踏まえた収量との比較では生産現場の実態に合わなくなってきた」
このように公表した上で、今後、収穫量調査におけるふるい目をこれまでの1.7ミリではなく1.8ミリから1.9ミリに変更することや、人工衛星など最新技術の活用のほか、生産者からの収穫量データを主体とする調査手法をとることを明らかにしました。