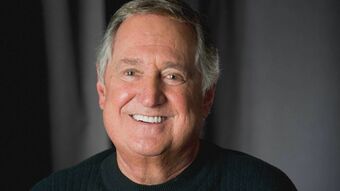医師の考えの違いで生まれた病院ごとの差

磯野:小野寺さんの考えは合理的で腑に落ちるのですが、静岡県の中で最前線で治療に当たっている静岡市立静岡病院が、「こういうふうにしても大丈夫でしたよ」といえば、そのやり方が派生して、東海地方に、全国に広がっていってもおかしくないと思いますが、広がらなかったですよね。なぜでしょうか?
小野寺:やはり、それぞれの医療のスタンスが違うからだと思います。感染管理を担当している医師の中には、「対策を緩和するなんて、絶対にそんなことはしない。この考えは譲れない」という人もいるわけです。例えば防護服一つをとっても「私はこの方法で感染が防げると信じているから、フルで装備しないと無理」と強く主張する人がいると、「ああ、そうか」となるわけです。それを誰かが説得するというのはかなり難しいですね。
静岡市でも静岡県でも、行政・保健所と病院の会議があって、その中で、どこの病院がコロナ患者をどのくらい引き受けるのか、感染対策はどうするんだといった話し合いがされました。それでも他の病院を説得するというのは、かなり難しかったと思いますね。「静岡病院はコロナに対しては最も緩い病院なので」というと、「ああ、先生のところは緩いですね。でも静岡病院に追随しようという根性はない」とおっしゃった病院長もいます。
磯野:根性の問題になっているんですね。
小野寺:多分、根性だと思います。
野路:「腹のくくり方」と言い換えてもいいかもしれませんね。
介護施設「お年寄りの幸せを守る」独自に感染対策緩和も
野路:静岡市立静岡病院のように、ここまでの対策でいいでしょう、それが合理的でしょうというふうに考えた病院や施設を、磯野さんは他にご存知ですか?
磯野:私はコロナ禍に調査をして、『コロナ禍と出会い直す』という本を書きました。調査で、鹿児島県にある「いろ葉」という介護施設を取材したんです。静岡市立静岡病院のように、「いろ葉」も非常に柔軟な感染対策をしていました。対策をガチガチにやってしまうと、お年寄りがコロナに感染するリスクは下がるかもしれないけれど、お年寄りの命、いわゆる人としての命というのを殺してしまう。施設に入ったら誰にも会えない。とにかく部屋に閉じ込めて、おむつにして、となってしまっては、むしろ体は弱るし、認知機能も落ちてしまう。何より人との交流が途絶えることで孤独にしてしまう。これはお年寄りの幸せを守ることではないという信念の下に、非常に柔軟な対策をとられました。
先ほど、小野寺さんが濃厚接触者の話をされました。病院や介護施設で、スタッフが濃厚接触者となって休んでしまい、仕事が止まることがあったと思います。なぜ仕事が止まるかというと、濃厚接触者を休ませてしまうからだと。そうすると、リスクのない人が働くことになる。そして次はまたその人たちが濃厚接触者となって休むことになる。すると濃厚接触者の無限ループが続いてしまう。そして働く人がいなくなる。だから「いろ葉」では、濃厚接触者の人は陽性者とみなして、陽性者として働いてもらうやり方をしたんです。すると、リスクのないスタッフが生まれます。そのスタッフには訪問介護などの外回りをしてもらう。そして陽性になったお年寄りは、陽性になったことのあるスタッフと、濃厚接触者になったスタッフがみるようにしたんです。結果的に、いつこの感染のループが収まるかというのも、ある程度予想がつくので、「あと◯日したら勤務態勢を戻そう」と見通しが立てられます。ループは長くても2週間くらいでいったん収まります。
マスクについても柔軟でした。マスクを着けたスタッフが近付くと、「お前は結核なのか」と言い出す方がいたそうです。結核が流行した時代を生きた方でしょう。マスクを着けた顔は、誰が誰だか分からないので、お年寄りが怖がって大声を上げてしまうこともあったそうです。耳が遠い方も多いので、スタッフはお年寄りの耳元で「◯◯さん」と大声で話しかける。すると、いくらスタッフがマスクをしていても、マスクの脇から息が漏れるのでマスクを着けている意味がない。そうした試行錯誤の中で、この場面ではスタッフがマスクを外した方がいいよね、こういう時は注意しようという形で、柔軟に対応しながら、少しずつバランスをとっていった。そんな介護施設もあったんです。
私は「いろ葉」を何度か訪問しましたが、コロナ禍とは思えないくらい、お年寄りもスタッフも、皆さん本当に幸せそうに暮らしていらっしゃいました。もちろん、お年寄りは家族にも会えるんです。しかし「いろ葉」の近くには、一度入ったらもう誰にも会えませんという介護施設も、やはりあるんです。その、施設ごとのギャップがすごかったですね。「いろ葉」では1回、クラスター(集団感染)が発生しました。その時だけは、完全に面会を止めて、デイサービスの利用者の受け入れもやめました。「◯日頃には開所できるので、それまでは家でみてください」と言えば、家族も自宅での介護を頑張れるんですよね。
小野寺:介護施設で多分、一番難しかったのは家族への対応だと思います。そんなふうに対策を緩めて、もしうちのおじいちゃんおばあちゃんがコロナに感染したらどうしてくれるんだと、家族から追及されたらどうしようと。みんな、ハリネズミのようになって、自分の組織、施設を守ろうとしていましたから。その点が、介護施設にとっては大変だったのではないかなと思います。実際には「そんなことは起こらない」ということも、「起きたらどうしよう」と怖がって、多くの施設が、「いろ葉」のように踏み切れなかったのだと思います。
磯野:確かに、最初の半年、または1年ぐらいは(怖がって緩和に踏み切れないのは)仕方がないと思います。しかしそれを、3年、4年と続けてしまう。今でも続けている病院や施設があります。それは、やはり一つの病院、一つの施設のみならず、日本社会の大きな問題点で、コロナ禍に限ったことではないんですよね。この点が、小野寺さんのおっしゃるような、「根性」という話に集約されてしまって、小野寺さんのような、非常に特殊な考え方の人にしかできない対応策だった、特殊な病院にしかできない、特殊な事例だった、という理解がなされがちです。そうなってしまうと、静岡市立静岡病院や「いろ葉」がされた非常に重要な対応策が未来に広がっていかないと思います。
小野寺:確かに、なぜもっと強く周りの病院に言わなかったんだ、働きかけなかったんだという批判はあり得るだろうと思います。
磯野:言ってもだめでしたよね、きっと。