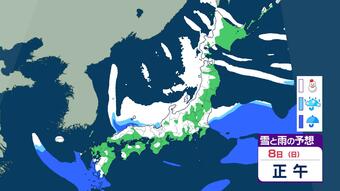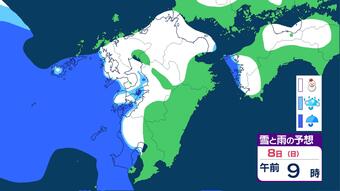猫の殺処分数ワースト1位だった長崎市が、2024年度「殺処分ゼロ」を達成する見通しが示されました。背景にあるのは、地域ぐるみで進められてきた「猫との共存」の取り組みです。
猫にとって「住みやすい町」とされる長崎市。気候が温暖で斜面地が多く車の通らない路地が多いことが一因と考えられており、野良猫への無責任なエサやりによる繁殖で猫の殺処分が多い状態が続いていました。
市の発表によりますと、長崎市動物愛護センターで殺処分された猫は2003年には4047匹。2009年~2017年までは9年連続で全国ワースト1位となり、その後もワースト3位以内が続いていました。
しかし2023年度には73匹まで減りワースト7位に、2024年度には初めてゼロとなる見込みです。
「共存」に向けた取り組み
「殺処分ゼロ」達成の背景には、地域住民と行政が連携した“共存の道”の模索があります。
野良猫の不妊化と地域ぐるみでの管理を行う「地域猫活動」の一環として、飼い主のいない猫の不妊手術費用を補助する「まちねこ不妊化推進事業」を進めたほか、2023年度からは離乳前の子猫を市民が預かり育てる「ミルクボランティア制度」をスタートさせました。
ミルクボランティア制度
生まれたての猫は2~3時間おきの授乳や排泄ケアなどが必要なため公的な施設では対応できず、センターでの殺処分の多くを離乳前の子猫が占めていました。
この現状に対応するため、市では民間と連携し自宅などで一定期間預かってミルクや健康管理などを担い、センターに返す「ミルクボランティア制度」を始めました。40頭以上がこの制度を利用し、これが殺処分ゼロの達成につながったとしています。
また去年「犬猫殺処分ゼロへの挑戦」を掲げ長崎市が実施した「クラウドファンディング型ふるさと納税」で、目標の300万円を上回る350万円超が集まり活動を支えました。
市ではボランティアを始めとした協力で達成できたとしており、今後も市民と連帯して猫と共存する町作りを進めていきたいとしています。
かつて“ワースト”だった街が、共存のモデルになろうとしています。