自治体に委ねられる「避難情報」の判断
また、地震発生時、津波注意報や警報などの発表以外に住民の避難の指針の一つとなるのが自治体からの情報です。
自治体の津波避難の情報に関しては内閣府のガイドラインがあり、一般的な対応としては「避難指示を出して避難を促す」としていますが、一刻も早く伝えるために避難の促し方は「自治体の実情に応じて工夫する」とも示されています。

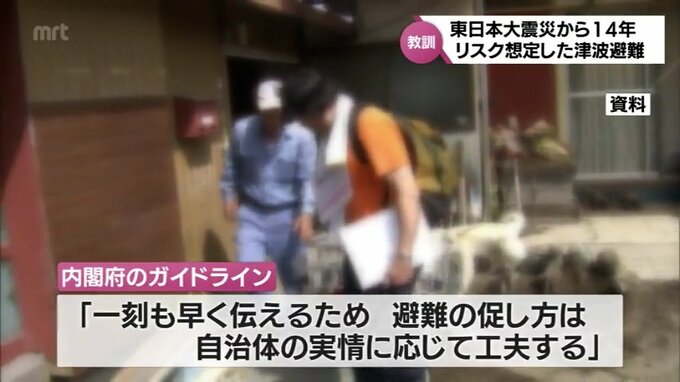
そのため、避難情報の判断は各自治体に委ねられていて、宮崎県内でも、去年8月と今年1月の地震で自治体の対応が分かれました。
このうち、宮崎市では、市の地域防災計画で津波注意報以上の場合は「避難指示」を出すとしていましたが、去年8月の地震の際には「避難指示」を出さず、防災行政無線などで避難を呼びかけました。

(宮崎市危機管理課 井久保利浩課長)
「宮崎市の場合は海岸線がかなり長くなっているので、防災行政無線を通じて避難を呼びかけ、SNSなどやテレビ・ラジオを通じてしっかり呼びかけをした」

一方、今年1月の地震では津波注意報を受け、「避難指示」を出しました。
(宮崎市危機管理課 井久保利浩課長)
「本来であれば、行政的に避難をしっかり呼びかける意味で、本来の『避難指示』を出すべきだったというところがあり、その反省をもとに、1月に関しては『避難指示』を出しました。行政としてもしっかり『避難してください』という呼びかけの一つ強い注意喚起ができたのではないかと思います」















