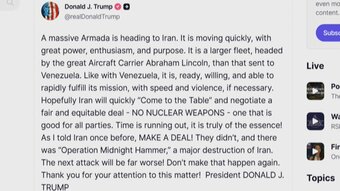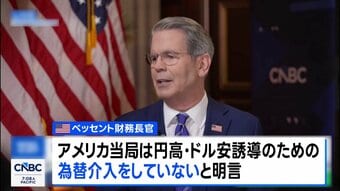「質的公平性」やSNS情報への対応などが見直しの論点に
アンケート最後の質問では、見直しにあたって、どのあたりが大きな論点になると考えるかを尋ねたが、特に「放送法の『政治的公平』に対応する各社の独自ルールも論点に含まれるか」と「SNSを意識した論点も含まれるか」も尋ねた。
その結果、この質問に回答した4局すべてが、検討の際に選挙における「政治的公平」について意識することを認め、中でも民放2局は「質的公平性」を論点として重視する姿勢を示した。
また、選挙時のSNS情報への対応については、4局とも論点となることを認めている。
NHKは、「放送法や公職選挙法の規定に則って、選挙の公平・公正を損なわないようにしながら、インターネット空間で広がる情報にどのように対応していくかは論点の1つになると考えている」とした。
日本テレビは、具体的な論点として以下の3点を挙げた。
● 政治的公平の「質的公平性」担保について
● (質問2への回答で示した各種の)施策実施に当たってのリソース確保について
● 取材記者や出演者に対する取材現場およびSNSや動画共有サービス上での誹謗中傷・ 威圧的行為などの対策について
TBSテレビは、「投票前の報道のより一層の充実、バランスや公平性のあり方、地上波、デジタル、それぞれで、どのような報道を行うのか、などが論点になると考えています。またSNSで発信される情報に向き合うことも含まれます」と回答。「デジタル」も含め、トータルで選挙報道を考える姿勢を示した。
フジテレビはまず、「選挙候補者掲示板の悪質な利用例や、当選を目的とせず、他の候補の応援を行うための立候補という、いわゆる『2馬力選挙』の問題、選挙演説にかこつけた特定の個人・団体への誹謗中傷などの行為等を、どのように捉え、法律でどこまで規制するかが焦点になると考えている」して、最近問題化している異例の選挙戦術などへの対応を挙げた。
そして、「政治的公平」については、「放送時間等で厳密に各候補に振り分けるなどの、いわゆる『量的公平性』よりも、選挙報道全体として、各政党、各候補に対する『質的公平性』を重視して報道することが重要との立場で報道を行っている。どのようにこの『質的公平性』を担保するかについては、様々なケースについてその都度、関係部署との協議を入念に行い、バランスに常に配慮しながら、判断を行っている」として、日本テレビと同様に「質的公平性」の担保について言及した。
さらにSNSを意識した論点については、「常日頃から関係部署との協議の対象となっており、SNSを利用した選挙の功罪を客観的に分析するとともに、SNSから発信される情報のファクト・チェックを行って、十分な裏付け取材・調査に基づいた報道を行うことに努めている」としつつ、「SNS等で虚偽情報が広まり、有権者の投票行動に大きな影響を与えると考えられるケースについては、『そうした社会現象が起きている』という情報も含めて、有権者への判断材料となる情報について発信することが重要だとの認識に立ち、報道を行っている」として、SNS関連の報道に力を注いでいることをアピールしている。
今回のアンケートを通じて、テレビ各局も従来の選挙報道について問題意識を高め、その見直しに向け真摯に取り組んでいることが浮き彫りになったと思う。テレビ各局のアンケートへのご協力にこの場を借りて改めて感謝申し上げる。
国民が選挙でどの候補者、どの政党に投票するかを考える上で何の情報を参考にするか、一昔前は新聞とともにテレビの選挙報道が重要なポジションを占めていた。
メディア環境が激変し、そのポジションに再び近づけるどうかは未知数だが、7月に見込まれる参議院選挙では、昨年とは一味違った報道がみられそうだ。“本気になったテレビのアップデート”に注目したい。
(「調査情報デジタル」編集部)
〈各局アンケートの質問文〉
質問1【選挙報道をめぐる基本認識と検討状況】
御社は「現在のテレビの選挙報道」が置かれている状況についてどのように考えていますか?
そして、これまでの選挙報道を見直すべく検討の必要があると考えますか?
あるいは、すでに検討を始めておられますか?
*1で「検討を始めている」、または、「今後、検討の予定あり」と回答された場合、以下の質問にもお答え願います
質問2【検討の方法やスケジュール】
検討は、どのような形(規模やスケジュール)で進めますか(進めていますか)?
報道局以外の部署や系列局(民放の場合)も含めてですか?
外部の方からのヒアリングも考えていますか?
また、検討の結果を反映させるのはいつの選挙からを目指していますか?
質問3【具体的な論点】
見直しにあたり、どのあたりが大きな論点になるとお考えですか?
放送法の「政治的公平」に対応する御社の独自ルールも論点に含まれますか?
また、SNSを意識した論点も含まれますか?
〈各局の回答・全文(チャンネル番号順)〉
NHK
《回答者》
日本放送協会
《質問1への回答》
メディアを取り巻く環境が大きく変化する中、NHKは公共放送として、視聴者・国民が「知りたい」と思うことに応えていく責務があると考えており、昨年来、民主主義の基盤となる選挙報道のあり方について検討を進めている。
《質問2への回答》
ことし夏の参議院選挙なども見据え、報道局が中心になって、各地域放送局など、さまざまな意見を踏まえて検討を進めている。
《質問3への回答》
放送法や公職選挙法の規定に則って、選挙の公平・公正を損なわないようにしながら、インターネット空間で広がる情報にどのように対応していくかは論点の1つになると考えている。
日本テレビ
《回答者》
日本テレビ 報道局次長 中村光宏
《質問1への回答》
私たちは「現在のテレビの選挙報道」は、3つの大きな課題を抱えていると考えています。
1) これから国を担う若い世代の多くがテレビで選挙報道を見ていないこと
2) 投票日前に有権者の投票行動に資する十分な情報を発信できていないこと
3) 選挙期間中にSNS上で拡散する誤情報や真偽不明情報に対応できていないこと
こうした点について見直す必要があると考え、検討を進めています。
《質問2への回答》
検討は、報道局内で昨年の東京都知事選後から、選挙関連部署の所属長以上を中心に、 課題ごとに議論しながらPDCAサイクルで進めています。
様々な場を利用して他部署や系列局とも共有し議論していますし、外部の方からも様々な 機会に御意見を伺い、参考にさせていただいています。
検討結果は、昨年の衆院選から反映させています。
上記質問1での回答 1)については、動画配信コンテンツとして、衆院選の公示後から連日、各党の政策をめぐる議論や投票日当日には開票速報や今後の日本の課題などを生配信しました。
回答2)については、衆院選の公示前後あたりから投票日までの「選挙運動期間」に、地上波の基幹ニュース番組で、党首討論のほか、政策テーマごとの各党公約比較や注目選挙区情勢、BS討論番組では、各党の政策担当議員による討論などを展開しました。
また投開票前々日の25日金曜日には、与党過半数維持ギリギリの情勢という世論調査結果を踏まえ、政権交代の可能性にも踏み込んだ分析を報道局長が解説。投票締め切りまでに30万回以上の再生がありました。
回答3)のファクトチェックについては、これまでも可能な範囲で行ってきましたが、引き続き取り組んでいく考えです。
《質問3への回答》
● 政治的公平の「質的公平性」担保について
● 上記 質問2の回答1)2)3)の施策実施に当たってのリソース確保について
● 取材記者や出演者に対する取材現場およびSNSや動画共有サービス上での誹謗中傷・ 威圧的行為などの対策について
テレビ朝日
《回答者》
テレビ朝日報道局
《3つの質問への一括回答》
選挙報道につきましては、その都度社会的情勢に鑑みながら、視聴者の知る権利に応じられるよう改善を図っております。
TBSテレビ
《回答者》
TBSテレビ報道局政治部長 岩田夏弥
《質問1への回答》
有権者が選挙で投票する際の判断材料を、より丁寧に伝えることが求められていると考えています。選挙報道をより良いものにするための検討を始めています。
《質問2への回答》
報道番組の制作を担っている編集長やデスクが中心となり、定期的にミーティングを行っています。テーマに応じて、報道局以外の部署や系列局の担当者も参加しています。また社外の識者にも、ご意見をうかがっています。検討結果については、最終的には夏の参院選での反映を予定していますが、それより前の千葉県知事選、東京都議選などでも、反映させられる部分は反映させていきたいと考えています。
《質問3への回答》
投票前の報道のより一層の充実、バランスや公平性のあり方、地上波、デジタル、それぞれで、どのような報道を行うのか、などが論点になると考えています。またSNSで発信される情報に向き合うことも含まれます。
テレビ東京
《回答者》
テレビ東京 執行役員 報道局長 小松澤 恭子
《質問1への回答》
選挙報道のみならず、マスメディアの報道全般に関わる状況の変化を感じております。
フジテレビ
《回答者》
フジテレビ報道局取材センター政治部長
《質問1への回答》
SNSやネット利用者の拡大により、有権者がこうした媒体を利用して選挙関連の情報収集を行うケースが飛躍的に増えている現状に鑑みて、「現在のテレビ選挙報道」の見直しは常に行っていかなければならないと考える。昨今のSNSやネットでの情報や、そうした情報をもとにした社会現象などについても、地上波やオンライン原稿等の報道の中で幅広く取り上げるべく、すでに取り組みを始めている。SNSやネットの情報には、十分な事実確認をすることなく流布している、いわゆる「偽」情報も多く含まれていることから、そうした「偽」情報に関するファクト・チェックや、虚偽の情報によって投票行動への影響が懸念されるケースについては、客観的な裏付け取材・調査を行いながら、社会全般に警鐘を鳴らすことも重要だと考え、客観性・公平性に配慮しながら報道にあたっている。
《質問2への回答》
前回の東京都知事選での「石丸現象」や、兵庫県知事選等で明らかになったように、SNS等で流される情報や動画が有権者の投票行動に与える影響は、無視できないものとなっていることから、国政選挙、地方選挙ともに、すでに報道機関としてできる「客観性」「公平性」等の原則に基づいたファクト・チェックや、報道の在り方などに関する検討は、社内の報道局、情報制作局、編成局など関係の局、関係の部署を横断して進めてきている。
また、全国の系列局との間でも、頻繁に役員レベル、局長レベル、取材部門のデスクレベルなどで、全局が集まる協議の場で議論をしてきており、各地方の自治体選挙のタイミングでは、放送法や公職選挙法などの法令に照らし合わせながら、どういう形での報道ができるかをその都度詳細に議論し、放送・オンライン出稿等に結び付けている。
外部の専門家なども交えた協議の場についても、様々な機会に現状の選挙報道の問題点等について意見をうかがう場を設けて、関係部局、取材部門などとの議論を行い、改善に努めている。
様々な場での検討結果を反映するタイミングについては、すでに、各地で行われている地方選挙の報道でこうした取り組みを反映させてきており、今夏行われる予定の東京都議会選挙、参議院選挙等の場でも、反映させていく考えである。
《質問3への回答》
選挙候補者掲示板の悪質な利用例や、当選を目的とせず、他の候補の応援を行うための立候補という、いわゆる「2馬力選挙」の問題、選挙演説にかこつけた特定の個人・団体への誹謗中傷などの行為等を、どのように捉え、法律でどこまで規制するかが焦点になると考えている。放送法の「政治的公平」については、放送時間等で厳密に各候補に振り分けるなどの、いわゆる「量的公平性」よりも、選挙報道全体として、各政党、各候補に対する「質的公平性」を重視して報道することが重要との立場で報道を行っている。どのようにこの「質的公平性」を担保するかについては、様々なケースについてその都度、関係部署との協議を入念に行い、バランスに常に配慮しながら、判断を行っている。
SNSを意識した論点も常日頃から関係部署との協議の対象となっており、SNSを利用した選挙の功罪を客観的に分析するとともに、SNSから発信される情報のファクト・チェックを行って、十分な裏付け取材・調査に基づいた報道を行うことに努めている。
SNS等で虚偽情報が広まり、有権者の投票行動に大きな影響を与えると考えられるケースについては、「そうした社会現象が起きている」という情報も含めて、有権者への判断材料となる情報について発信することが重要だとの認識に立ち、報道を行っている。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。