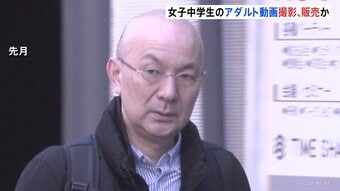「自立」ではなく「自律」を “米中冷戦”の今、日本外交の進むべき道
ーー今後の安全保障、国際関係における日本の立ち位置については。
長島昭久 総理補佐官:
やっぱりバイデン政権のときとトランプ政権では相当違う心構えでやらないといけないんじゃないか。それはやっぱり発信。発信があまりにも目まぐるしいので。バイデン政権はそこが落ち着いていましたから与しやすいというところはありました。
しかしね、国際関係って本質は、構造は変わってないんですよ。
僕は、これをどう呼ぶかは別にして、米中の間は「熱戦にならない冷戦」だと思ってるんですよ。それは昨日今日始まったわけではなくて、2014年にロシアがクリミア半島を併合した。そして南シナ海に中国が人工島を作った。ここから始まってるんだと思うんです。これがどんどんどんどん構造化してきてるっていうのが現状ですから。
基本はそこに置きながら、日本の立ち位置、アメリカとの関係やヨーロッパとの関係、そして中国との関係を決めていくっていうことが大事だと思っていて。私は安倍・菅・岸田・石破、これはずっとそういう意味では一貫している流れだと思ってるんで。私はそんなに急カーブ・急ブレーキを踏む必要は全然ないと思ってます。
その中で、日本外交が進むべき方向性。「自立」ってよく言うじゃないですか。対米自立ってね。右の人も左の人もアメリカに対して。ある意味では石破首相も昔はそういう感じがあったけど。私はね、アメリカとの関係で物事を考えるんじゃなくて、「自律」。自分を律するということはつまり自分の自由な空間を増やす、自分が自由に動けるようにするっていう意味ですよ。そういうことを目指すべきだと。
そのために何が必要かといったら、アメリカと離れる。アメリカといちいち喧嘩するんじゃなくて、日米同盟を強化しながら地力をつけて、自分で自分のことを処理できるような実力をつけつつ、仲間を増やす。同志国との連携。だからクアッドが大事だし、日米韓や日韓、日米豪も大事だし、もしアメリカが少しずつ国際社会に対するコミットメントを減らしていくようだったら、日本が代わって前に出てですね。例えばインドとインドネシアと日本の間で何か…オーストラリアも入れて、もう一つのクアッドを作ってもいいし。
あるいは、今「IP4」ってあって、アジアでは日本・韓国・オーストラリア・ニュージーランド、この4か国がNATOと特別な関係を結んでるんですね。だからそういうところを使って日本を信頼して、日本を中心に重層的に多国間の関係を作っていく。こういうことが日本外交にとっては日本の戦略的自律の可能性を広げていく。僕は今自分としてはそういう方向に日本の外交を構想したいなと思ってます。