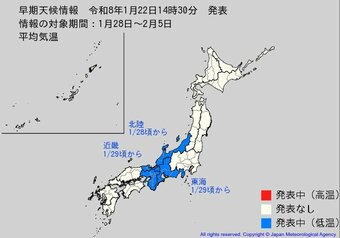しかし、特捜部が「P3C」の疑惑に本格的に切り込むことはなかった。
児玉の先にいる政治家に、どうカネが渡っていたのかは解明できなかった。
前述の通り、事件発覚直後、東京女子医大の児玉の主治医が「脳梗塞の後遺症」との診断を提出、「証人喚問」は実現しなかった。
この主治医による児玉の「疑惑の診断」については稿を改めて記したい。
さらにロ社との交渉に立ち会うなど、事件のキーマンとされた児玉の通訳、福田太郎も急死を遂げた。
福田は「巣鴨プリズン」以来、児玉の右腕だった。
終戦後は「GHQの通訳」として採用され、 コーチャンが来日した際も通訳、助手として尽力した。
福田は事件発覚直後の2月8日に入院、特捜部の取り調べに対しても非常に協力的だったとされるが、6月10日に死亡した。
この福田の死と児玉の入院により、「児玉ルート」の捜査は大きな壁に直面したのだ。
そのため特捜部は、証拠関係がはっきりしていた「丸紅ルート」の民間航空機「トライスター」の疑惑に焦点を絞り、ロ社から「丸紅」を通じた田中角栄へのワイロを軸に事件を組み立てた。
しかし、「児玉ルート」の捜査が見送られた背景には、何らかの大きな力が働いていたとの見方もある。
堀田はのちにこう回想している。
「米側から取り寄せたSEC証券監視委員会の捜査資料に、『P3C』に関するものはなかった。 どうも、『P3C』に関する資料だけが、あらかじめ意図的に抜き取られていたように感じた。状況証拠だけでは、なにもできなかった」
米公聴会でも、日米間の「軍事利権」にかかわる「工作資金」の流れについては、いっさい検証されることはなかった。
また堀田が立ち会ったコーチャン、クラッターの「嘱託尋問」においても、「P3C」に関するやりとりの記録はなかったとされる。
歴史にイフはないが、もし児玉や福田への取り調べで「P3C」の不正を裏付けるような供述が得られていれば、特捜部は児玉と福田をただち逮捕して、本格的に「児玉ルート」を解明することは、果たして可能だったのだろうか。
児玉が「CIA」の協力者であったことが、「児玉ルート」の解明を阻む要因になっていたのではないかとの指摘もあった。
ジャーナリストの立花隆は、著書でこう述べている。
《ロッキード社の協力なしには、対潜哨戒機「P3C」の全貌を解明することは不可能だった。さらに、関係者が「P3C」問題には触れまいとする姿勢で一致していた。 検察もまた、「田中角栄がワイロを受け取った」という最重要事実を立証できれば、公判を維持して、有罪判決に持ち込むことは可能と判断していた。
ロ社の意向や関係者の思惑が「トライスター」に議論を限定させる中で、検察はその範囲内で事件の決着を図ったのである》
そしてこう指摘する。
《「P3C」については触れまいとする意思。その意思はアメリカの意思、つまり対ソ戦略の一環として存在する、日本における「対潜哨戒機P3C」の形成に、障害が起きないようにとの意思が働いたのではあるまいか》(田中角栄研究 全記録)
政治評論家の麻生良方は、ロッキード裁判が始まる前のインタビューでこう話している。
「事件の本筋は P3Cの日本への売り込みだが、検察はなぜか派生的な全日空へのトライスターの導入に、捜査を集中させた。
田中角栄を釣り上げたから、 国民感情が収まったなど、とんでもないことだ」
(TBSニュース 1976年9月30日)
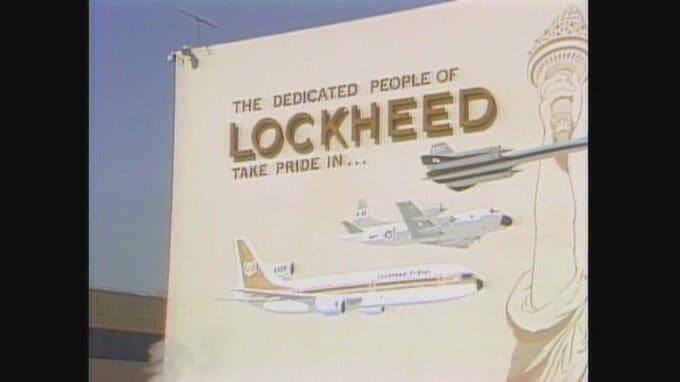
丸紅側が突如、持ち出した「P3C」疑惑
田中角栄逮捕から半年後の1977年1月27日、ロッキード事件「丸紅ルート」の初公判が開かれた。
検察側が証拠で積み上げた事実を述べる冒頭陳述で、「P3C」の扱いに注目が集まった。しかし、「P3C」について触れたのは、わずか以下の数行であった。
《小佐野賢治はコーチャンから「P3C」の売り込み工作を依頼されて、了承した。
その際に、小佐野は「P3C」の売り込みに成功した場合に『児玉が取るべき報酬が少ないのではないか』とコーチャンに文句をつけ、児玉の成功報酬を「50機の受注に対して、25億円」となる契約書を作らせた》
この「25億円」の契約については、すでに捜査段階でも明らかになっており、新しい事実とは言えなかった。
ロッキード裁判は一審判決までに「6年半」の長期にわたり、「191回」の公判が開かれるという異例の展開となり、検察側と弁護側の容赦のない激しいやりとりが続いた。
一審が佳境を迎えた1982年12月15日、堀田は被告人質問で、田中角栄にこう呼びかけた。
「田中が検察官の質問に応じることを希望する」
すると、「呼び捨て」された田中は顔を紅潮させながら堀田をにらみつけた。
「質問に応じない田中さんにこう言ったら、ほんとに動物的というか、すごい気迫で『この無礼者!』と怒鳴るように言い返してきた。その怒りの防御というか、迫力がすごかった。
この勢いで迫られたら、派閥の新人議員なんて、たじろいでふっとんじゃうだろうと思った。
でも私は正論しか主張してないですから、たじろぐ理由もなく、お互いに無言の火花を散らした。もっとも緊張した場面だった」
(堀田インタビュー TBS「筑紫哲也ニュース23」 1999年5月10日)

検察側は、一審判決までの6年半、組織の威信を賭けて「ロッキード裁判」に注力した。その間、多数の特捜検事が「補充捜査」にあてられたため、新たな政治家の汚職摘発は、10年以上も鳴りを潜めた。そんな検察の執念もあり、識者やマスコミの予想でも「有罪判決」はほぼ確実視されていた。
ところが、1983年9月、翌月に一審判決を控えた土壇場で、予想外のことが起きる。丸紅側が、最終弁論で「P3C」のことをあえて持ち出す「戦法」に出たのである。
丸紅の檜山元会長の弁護団は最終弁論でこう切り出した。
「コーチャンは、ロッキード社が力を注ぐ『P3C』の対日売り込み工作に、支障が出ない形で証言する必要があった。事実、『5億円』を『トライスター』と結びつけて事件を構成することによって、P3C隠しに成功していた。日本の検察も『P3C』との結びつきを、極力避けようとするコーチャンの筋書きに従った」