■「計画運休」の規模が変わる、その理由は?
4年前、2018年の台風24号、左側がその時の進路図です。一方、右側が9月の14号の進路図です。ともに九州から東北地方へと縦断するコースでした。

4年前の24号について、仙台管区気象台は、最大瞬間風速を県内の陸上で▼30から35メートルと予想していました。
実際にはどれくらいの風が吹いたのでしょうか?
2018年の台風24号が接近した際の当時の映像です。

仙台では、▼37メートルという観測史上3位の風を記録しました。
このときJR東日本は、仙石東北ラインや常磐線など広い範囲で計画運休を実施し、多くの区間が6時間以上に渡って運転を見合わせました。

そして、9月の台風14号でも仙台管区気象台は、ほぼ同じ▼35メートルの最大瞬間風速を予想していました。そうなると鉄道の運行にも同じ程度の大きな影響が出そうな気がしますが、実際JRが計画運休を発表したのは、県内では気仙沼線の一部区間だけでした。

同じ規模の台風なのに計画運休にずいぶん差があります。これはどういった理由があるのでしょうか?
実は、JRに情報提供するウェザーニューズで、4年前とは違い今回の台風は、衰えながら宮城に近づくと予想していたのです。
ウェザーニューズ鉄道気象チーム 山下幸宏チームリーダー:
「たしかに西日本にいたときには、我々もかなり強まるということで警戒はしてましたが、そのあとは弱まるという傾向が顕著でしたので、そこまで大規模に(運休)ということは、ないかなと考えていました」
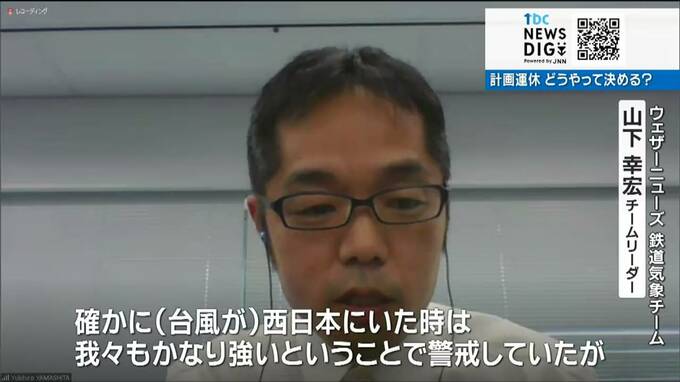
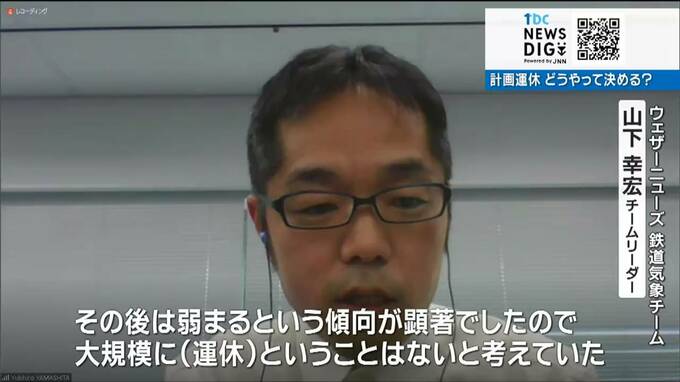
そして、当日の朝、台風はちょうど宮城を通過していきましたが、最大瞬間風速は最も強かった石巻でも▼22.2メートルにとどまり、気仙沼線以外の路線は平常運行となりました。そうなると、なぜ気仙沼線だけが運休となったのか?














