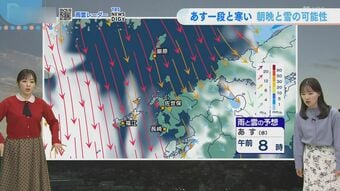寒い日の食卓の定番といえば「鍋」ですがその鍋に欠かせないのがいま旬を迎えている「長ねぎ」です。雲仙市には海外にも出荷されている人気のブランドねぎがあります。20年前、亡くなった父親から継いだ畑で「長ねぎ」作りを究めた男性を取材しました。

長崎県雲仙市国見町、「栗原ねぎ」の生産者 栗原光博さんです。およそ11ヘクタールの畑で年間300トンの長ねぎを栽培しています。福岡や大阪、名古屋などの他台湾へも出荷されています。質の高い特産品として雲仙市が認定する「雲仙ブランド」にもなっているこのねぎの秘訣は土にあります。
栗原さん
「うちの土はふわふわしていますよ。ねぎはね元々ヒマラヤの近くが原産で、そこは排水が良くって雨が降らないところだから排水が良いところが良く育つ」
経営規模の大きさやその人気から全国のねぎ農家が集まるサミットで講演も行っている栗原さん。就農したのは2004年、不慮の事故で父・厚夫さんが急死したのをきっかけに勤めていた建設会社を辞めネギ農家となりました。しかしー
栗原さん
「甘かったですね。選別も何もわからなくて、ただねぎの皮むきをして箱に入れて出すだけだったから、すごい買い叩かれましたね。50円ぐらいですね、1箱、これ10パック入って」
どうやったら美味しいねぎが育つのか?栗原さんが最初に目をつけたのは肥料でした。含まれている成分や化学反応による効果を考えました。
栗原さん「甘いというのは炭水化物。光合成をしたら、炭水化物でしょ、CHOになるでしょ。どうして美味しくなるんだろう?それをやっぱりお客さんやバイヤーに説明しないと納得して買ってもらいたいしね」
追究したのは作り方だけではありません。
栗原さん「まずこのパッケージですね、パッケージを覚えてもらうこと。(直売所は)みんなね、すごい自分の野菜をPRしている。PRするチャンスなんです」
農家直売所大地のめぐみ 渡邉晴彦さん「お客様の認知度も高く、売れ行きの方も結構いいですし、また問い合わせも結構多い商品になっている」
飽くなき「探求」が功を奏し、栗原さんのねぎはいま、「他に代えられない味」として多くの人に求められています。全国からの注文に応えるために栽培面積も徐々に拡大。ねぎ作りを始めた当初と比べおよそ7倍になりました。いまは15人の外国人従業員も抱えています。
栗原さん
「インドネシア、中国、ベトナム、カンボジア。仕事が上手。助かっています。彼らがいなかったら(栽培は)できないね」
今や、1箱2000円の人気ブランドとなり大忙しの栗原さんを支えているのが息子の直樹さんです。

息子・直樹さん
「一緒にやろうやって言ってくれて。なら、俺も頑張ってみようと思って」
研究熱心な栗原さんに触発され、直樹さんは「土壌医」の資格を取得しました。
直樹さん
「(栗原さんは)まだまだ雲の上の存在です。まだ修行中なんで、まだまだ勉強することがたくさんあります」
もがき、究めて、20年。いま思うことがあります。
栗原さん
「収穫を目前に、父が亡くなった。『あとは任せたぞ』と俺に託したんかなって、それを感じました、今になってね。お盆には伝えたいですね、『売り上げが上がったよ』とか。どんな顔で見てるんやろ…喜んでいると思うよ」
父から受け継いだ栗原家のねぎを息子へ、さらにその先へ繋げていくのが栗原さんの目標です。
栗原さん
「一度食べたら忘れられないねぎとして伝わっていったらいいなと思います。ずっと全国でずっと知られたいですよね、栗原ねぎ。」
栗原ねぎをもっと多くの人たちに味わってほしい。栗原家は、これからも「至極の長ネギ」を追い求め続けます。