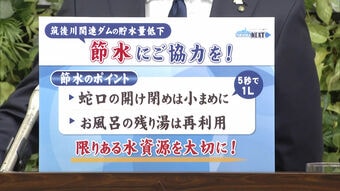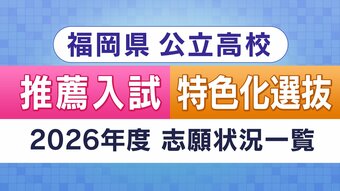震源地は「生き仏」めぐり敏感な都市
中国当局が被災者の救助や、その後の復興に懸命になるもう一つの理由を、私の目から解説したい。それは震源地がシガツェということと大きく関係している。
チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマを「ダライ・ラマ14世」と紹介した。「14人目のダライ・ラマ」「14代目」ということだ。チベット仏教は「すべての生き物は輪廻転生する(生まれ変わる)」という教えに基づく。中でも観音菩薩の化身(=生き仏)とされるのがダライ・ラマ。その死去後に、生まれ変わりの男の子を探して後継者にする伝統が続いてきた。今の14世は、13世が死去したのち、2歳の時に位の高い僧侶たちに認定された。
ダライ・ラマに次いで高い位にある「生き仏」がパンチェン・ラマ。歴代のパンチェン・ラマが座主を務めてきた由緒ある寺が、このシガツェにある。
先代のパンチェン・ラマ10世が1989年に死去した後、ダライ・ラマはその生まれ変わりとして、当時6歳の少年を見出し、パンチェン・ラマ11世に認定した。だが、中国側はそれを認めず、別の少年を独自にパンチェン・ラマ11世にし、その人物は今もシガツェで活動している。一方、ダライ・ラマ側が先に見出した少年(=すでに35歳になっているはず)は、中国当局の手によって消息が不明のままだ。国外にいるダライ・ラマは、中国側の決定をどうすることもできない。
チベットに住む人たちにとっては、崇拝するダライ・ラマ14世が選定した「消えた11世」こそ、本当のパンチェン・ラマだ。中国政府が認め、現在、シガツェで活動するもう1人のパンチェン・ラマを「本物のパンチェン・ラマではない」と考えており、それがチベット族の共産党不信の一つになっている。その不満の渦が巻くシガツェで、大きな地震が起きた。
共産党政権にとって、シガツェは敏感なチベットにおいても、とりわけ敏感な町だ。習近平主席をはじめ中国当局が被災者の救助や、その後の復興に懸命になる、もう一つの理由がそこにある。そのような角度から、今回起きた地震を見ると、自然災害とは別の一面も見えてきそうだ。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。