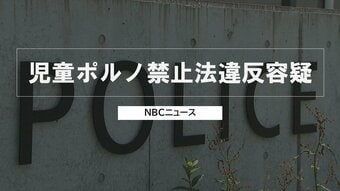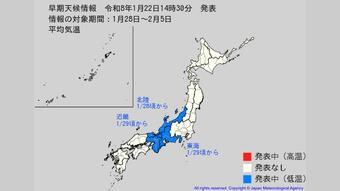11年後に生まれた長女が認定

カネミ油症被害者 森田安子さん:
「私には3人の子どもがいます。3人とも生まれた時から体が弱い方でした。倦怠感、頭痛、めまい、皮膚疾患、婦人科系疾患と、私と同じような症状が10代の頃から出始めた子どもたちは、もう20年以上通院治療を続けています。長女と長男は皮膚症状がひどく悲惨です。全身の皮膚が剥がれ落ちるといった表現が適切だと思います。年中皮膚を隠すような衣服しかきません」

「長女(1979年生まれ)は平成21年(2009年)に、現行の認定基準で認定されました。母乳と胎盤を通してPCB、ダイオキシン類が胎児に移行したことの紛れもない事実だと思います。長女の認定で、次世代被害者の救済に何らかの動きがあると思って、本当に期待をしました。でも油症研究班は全く無関心です。なぜ行動できるはずの立場の人たちが動いてくれないのか?子供たちは何も悪くないです。助けるという簡単なことが、加害企業も国もなぜできないのか?本当に不思議です」
カネミ油症をきっかけに製造禁止
日本のPCB生産は1954年に始まった。総生産量約5万9,000トン。このうちの96%は鐘淵化学工業(現カネカ)高砂工業所で製造された。

1968年のカネミ油症事件を契機に、その毒性や環境汚染が社会問題化し、1972年に法律でPCBの製造が中止になった。
未だ続くPCB処理の現状
PCBの処分は、約30年間に渡って全国で処理施設立地が試みられたが、地元住民らの反発からすべて失敗(39カ所で施設立地を断念)し、購入者による「保管」が続いた。この間、紛失や行方不明が相次いだ。(PCB使用機器約11,000台 が紛失:平成10年厚生省調査)
2001年にようやく「PCB廃棄物処理の特措法」が制定され、2004年に処理が開始された。
高濃度PCB廃棄物は環境省の特殊法人である「JESCO」中間貯蔵・環境安全事業株式会社が、低濃度PCB廃棄物は、都道府県知事が許可した民間の施設で処理されている。
高濃度は、2023年3月31日までに処理終了。低濃度は2027年3月31日までの処理終了が法律で定められている。
PCB処理にかかった費用はこれまでに総額およそ1兆円。うちおよそ2,000億円は国が負担、ほかは購入業者らが負担している。
企業の責任はどこへ?
PCBを製造・販売した企業の責任を問う法律はない。カネミ油症被害者が食べたPCBを製造した鐘淵化学工業(現カネカ)は、1987年に裁判で和解し、当時の原告に一人当たり300万円、総額約105億円の和解金を支払った。しかし、その後認定された患者への負担は一切行っていない。次世代被害者への言及もない。会社の「沿革」でPCB製造にも、カネミ油症にも触れていない。被害者との話し合いにも応じない。
カネミ倉庫は?
PCBが混入した油を販売したカネミ倉庫は資力に乏しい。当時小学生だった社長の息子が経営を引き継ぎ、認定患者に対し年間総額およそ1億円に上る医療費と1人年5万円の支払いを続けている。和解等にもとづき決まった一人当たり500万円の一時金は、医療費の支払いを優先することで強制執行しないこととされている。
健康な体を奪い、人生を壊した加害責任。資力不足を詫びながら「できることは全力で続けていく」との姿勢を示し、ある意味で被害者と共に逃げられない事件の重みを背負い続けている。同時に、毒性を知らせずにPCBを販売したカネカに対し、被害者救済の枠組みに入るよう求め続けている。カネカとカネミ倉庫は、名前こそ似ているが全くの別会社だ。