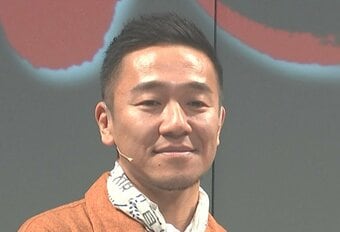ターニングポイントは2013年?日本アニメの海外進出のきっかけとは
野村:
今、世界を食らうと評されるぐらい日本のアニメに注目が集まっている背景としては、何かありますか。
中山:
動画配信が一番わかりやすいです。実は明確にコンテンツが増えてきたタイミングがあります。2013年です。
野村:
2013年ですか。
中山:
2012年までは5年ぐらいずっと、何度かアニメのブームがありました。海外における日本アニメブームですね。
「涼宮ハルヒ」シリーズが注目された時代はパッケージが売れていました。日本のアニメ会社が2000年~2006年ぐらいから出てきたときに、3000~4000億円規模まで成長しました。
それがなくなってしまって、2000億ぐらいの規模で5年ほど低調だったのが2008年ぐらいからです。
「やっぱり海外で日本アニメが流行るのは1個の夢だったね」というイメージです。
それが2013年にポンと2000億から2800億くらいになりました。
ここから勢いが止まらず、毎年上がっていって1.7兆円までワーッと上がり続けました。野村さん、2013年に何があったと思いますか?
野村:
なんでしょう。10年以上前ですよね。
中山:
『進撃の巨人』が2013年アニメ化したぐらいがちょうどいいプッシュになったと思います。
実質は2006年からあったCrunchyroll(アメリカの動画ストリーミングサービス)が、2009年ぐらいに『NARUTO』を正式配信しました。
中国でも2011年ぐらいに「土豆」(Tudou)や「bilibili」などが正規配信したのが2011~12年ぐらいです。
2013年は正規版でようやくみんな出そろって動画配信を始められた。
スマホが普及したタイミングも日本を含めて2012~2014年です。
モバイルファーストの動画配信がサブスクで月10ドルみたいなのがあるコンビネーションになったときに、作品も『NARUTO』や『進撃の巨人』『Re:ゼロから始める異世界生活』などが出てきました。
あの辺りっていろいろ良いタイトルが詰まっているので、そこから日本のアニメが一気に上がりました。
更に深掘りすると、2016年のVR元年があって「キズナアイ」などVtuberの原型ができましたが、明確にVTuberが入ってきたのは2020年です。
ホロライブと、ANYCOLORの「にじさんじ」が出てきました。
アメリカからの見え方で言うと「2010年代後半アニメ結構来ているな。『僕のヒーローアカデミア』も出てきたし、Vtuberも出てきた。これって何だろう、やたら全部2次元系だな」という印象です。
アンドリーセン・ホロウィッツの中だと『君たちはどう生きるか』とかジブリもひとつのファンタジーを根づかせた大きな作品であるような議論もされました。
我々からすると、アニメやゲーム、VTuberが全部合わさって、「日本のアニメ」が盛り上がっているっていうことだと僕は理解しています。
野村:
そうすると2013年にモバイルファーストとその配信の土壌が整っていたっていうことがあり、そこに元々あった名作アニメが供給されていたわけですね。
そこから2020年代にはそのVRが来て。最新のアニメも世界的ヒットするものがいくつか現れ、広まっていったことですか。