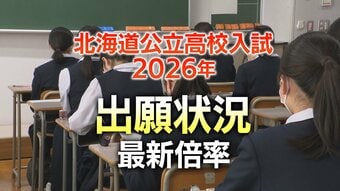■再犯防止へ変わる刑事司法
彼らの更生を阻んだものは何か。
犯罪を起こした人の社会復帰支援に詳しい立命館大学・森久智江教授(犯罪学)は、Bが服役した頃は、刑事司法が大きく変わろうとしている狭間にあったと語る。
立命館大学・森久智江教授(犯罪学)
「当時の刑務所というのは基本的には刑罰の賦課だけが目的とされていて、受刑者自身のそれまでの生き方や成育歴の中でどういった困難があったかなどを振り返るような場面は非常に限定されていた」
Bが2度目の服役から出所して7年後、国も再犯防止に向けて大きく政策を変える。2016年に再犯防止推進法が施行され、犯罪や非行に走った人たちが社会復帰をするため、地域社会において孤立することのないよう、住居や仕事、医療、福祉など官民が連携して支援していくことを目指すことになった。国の計画策定後、埼玉県が第1期計画をスタートさせたのは2021年。Bの死の前年だった。
そして2025年6月、日本の刑事司法は明治以来となる刑の種類を見直し「拘禁刑」が導入される。これまでの「懲役刑」や「禁固刑」がなくなり、再犯防止に向けた更生に大きく踏み出す。オープンダイアローグというフィンランド発祥の精神医療の手法などを取り入れながら、チームを組んで一人ひとりの受刑者の再犯防止に取り組む。
森久教授は、対話の効果が、Bのような妄想への治療にも役立つと考える。
立命館大学・森久智江教授(犯罪学)
「オープンダイアローグは自分自身や自分の置かれている状況を鏡のように客観的に見る形になる。こうした対話が、社会との関係性や自分と他者との関係性を本人が知るきっかけになることはわかっている。妄想で疑心暗鬼的になった自分の考え方を良い方向に向けられることができるのではないか」
Bの死から私たちはどんな教訓を得られるのだろうか。私の質問に森久教授は刑務所での医療ケアの充実が必要だとした上で、出所後の支援の課題を指摘した。
立命館大学・森久智江教授(犯罪学)
「出所した後も基本的には家族が責任を全て持たなければいけないような状況になっている。少年事件の家庭の状況は、家庭自体が何かしらの困難を抱えていることが多い。事件前とほとんど変わらないような状態で社会生活を送っていかなければいけない。再犯したというのは、ある意味その状況が変わらない以上、起こるべくして起こったという面がある。生活再建や施設内処遇を変えていかなければならない」