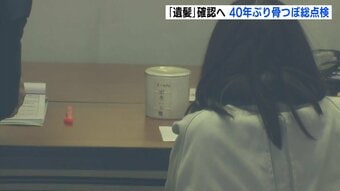移動しながら日本被団協の話をしたいんです。正面に見えるのが、あす10日、授賞式が開かれるオスロ市庁舎です。正時、午前8時や9時になるとチャイムが鳴ったりして、すごく荘厳な、きれいな市庁舎です。
その日本被団協なんですが、広島の方でも日本被団協がノーベル平和賞に選ばれたと聞いて、正式名称ってなかなか全員が言えるわけじゃないと思うんですが、日本原水爆被害者団体協議会という名前です。わたしが今回、取材に来た理由は、母方の祖父が日本被団協の初代事務局(藤居平一)だったことからです。
故・藤居平一(1996年没・広島出身)
ノーベル平和賞が贈られる日本被団協の初代事務局長
私財を投げ打って活動し、“被爆者運動の父” と呼ばれた
祖父は、私財を投げ打って活動に身を投じて、母とかに思い出話を聞くと、小学校のときに遠足の日があって、祖父から「遠足は勉強じゃないから、勉強を休んじゃいけないけど、遠足は休んで募金に行こう」ということで、いっしょにほかのきょうだいとたちと募金箱を首からぶら下げて、そごう広島店(広島市中心部)前に行ったりした経験があるそうです。

祖父の活動を紐解くと、日本被団協は「自らの経験をとおして人類の危機を救おうと決意し、誓い合った」というのがありました。それは、今回のノーベル平和賞授賞理由と完全に合致していて、今回の選考委員会も彼ら被爆者の経験やこれまでの活動が、これまでの核の不使用につながっていると。彼らが核のタブーを形成してきたということが授賞の理由になっていました。

ノーベル平和賞 授賞理由(抜粋)
「人類の歴史で今こそ核兵器とは何かを思い起こす価値がある。それは世界がかつて経験した最も破壊的な兵器だ。授与することで肉体的苦しみやつらい記憶を平和への希望や取り組みを育むことに生かす選択をした全ての被爆者に敬意を表したい」
まさに本当に人類の危機に、再び被爆者たちの経験が必要とされていると感じています。さきほど言ったように日本被団協は、日本原水爆被害者団体協議会ということで、定義として “被爆者” と “被害者” はちょっと違うんですけど、今回は被爆者の経験を授賞の理由にされていました。
もう一つ、祖父のよく言っていたのが、「広島・長崎の庶民の歴史を世界史にする」(藤居平一 連絡文書)という言葉がありました。これまで日本では前回の受賞が、非核三原則を掲げた1974年の佐藤栄作元首相。2009年にオバマ元大統領が核なき世界を提言して受賞しました。続いて近年、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)や今回の日本被団協のように、大国の指導者とか、なにか特殊能力を持った方がたではなくて、本当に一般市民・庶民が今回、祖父の言葉どおり世界史に刻まれる瞬間が訪れようとしていると感じています。
もちろん、被爆者の中には「お祭り騒ぎじゃないんだ」と、「そもそも原爆なんて落ちなければ、こんなことにならなかった」とおっしゃっている方もいらっしゃるので、あんまり盛大な拍手をもってという感じではないかもしれませんが、とにかく広島・長崎の経験をもとに、今ある平和とこれからの平和を考える機会にしたいと思っています。
青山高治 キャスター
オスロに到着された日本被団協代表団のみなさんの様子はいかがでした? 疲れとかだいじょうぶそうでしたか?
松本清孝 記者
やっぱり高齢の被爆者のみなさんが多いので「かなり疲れた」「寝られなかった」とおっしゃっている方はいらっしゃいましたが、やる気に満ちあふれているというか、これをきっかけに必ず世界をもっとよくしてやるという意気込みにあふれてるように感じました。