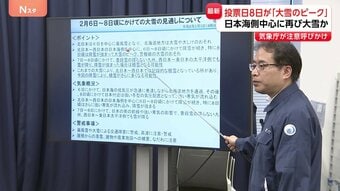子どもと先生の関係 親ができることとは
小川キャスター:
広い視座で振り返ると、いろんなものが見え、いろんな見方ができます。しかし、子どもはなかなか広い目線で見ることができない。そういった中で、先生との関係に不安を覚えるようなことがあったときに、どういう解決法があるのでしょうか。

てぃ先生:
これはいろんなケースがあるので、「絶対これ」とは言い切れないという前提があります。親は子どもたちに親心として、「こうしてみたら」とアドバイスをします。しかし、親自身も自分の子どもが実際に学校でどう過ごしてるのかを見ているわけではない。
例えば「あなたの方から先生に元気よく挨拶してみたら」みたいな、親からすると「これならできるんじゃないか」というアドバイスも、その子は「いやできないよ」と思っているかもしれない。でも親が言うからやってみようと思い、次の日学校に行ってみたけど挨拶することができなかった。そうなると、「学校でちゃんとできない自分」が積み重なり、親の優しさが逆にプレッシャーになって、余計行きたくなくなることがあります。
基本的にこういう問題は、子どもに「頑張ろう」と言うのではなく、親が学校側や担任の先生と話す機会を作った方がベターだと思います。その話し合う機会も、「学校は何やってるんですか」ということではなくて、「最近うちの子どうですか」というヒアリングから入っていくことが大事だと思いますね。
藤森キャスター:
いま教員の数も少ないと言われていて、負担を軽くしなければいけないという議論が真っ最中ですが、このあたりの時代背景もあるのでしょうか。

てぃ先生:
時代背景で言うと、昔は「先生」という職業に対してリスペクトがあったと思います。しかし最近いろんな報道を見ている中で、親も先生に対して不信感があり、いまは「親が先生たちを評価するような時代」に片足突っ込んでいるのだと思います。
小学校の先生たちとも話していてよく話題に上がるんですが、家庭の中で親が「今年の先生は外れだよね」みたいな話をするケースがあるみたいです。子ども自身は「なんか(先生と)そりが合わないな」くらいに思っていたものが、親のその一言によって「あの先生は駄目な先生」というふうになって、余計に行きたくなくなることがあります。
トラウデン直美さん:
一度不登校になってしまうと、復帰するのが結構大変だったりする。でも(子どもの)心のことを考えると、「行かなくてもいい」とも言ってあげたい。そこのせめぎ合いは難しいなと思います。
小川キャスター:
学校に行くことが正解とも限らないということがありますよね。
てぃ先生:
それは本当に家庭ごとに判断が異なってくるかなと思います。
小川キャスター:
個々のケースに真摯に寄り添い解きほぐしていく、ということになりますね。
================
<プロフィール>
てぃ先生
保育士16年目の37歳
育児アドバイザー
SNSの総フォロワー数200万人超
トラウデン直美さん
環境問題やSDGsについて積極的に発信
趣味は乗馬・園芸・旅行