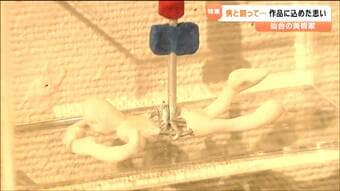13年前に東日本大震災を引き起こした海底の断層を調べる調査が、宮城県沖で行われています。深さ7000メートルの海底を掘削し断層に含まれる物質や力のかかり方がどう変化しているのか調べています。
調査を行っているのは、海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」で、今年9月に静岡県の清水港を出航しました。

その後、宮城県の牡鹿半島から220キロ沖合で掘削調査を開始。深さおよそ7000メートルの海底からさらに1キロ近く掘り進み、10月6日には、「コア」と呼ばれる地層の一部を引き上げることに成功しました。

「コア」はあわせて7本採取する予定で、各国から集まった地震学や地質学の研究者が分析にあたります。
日本科学未来館科学コミュニケーター 三浦菜摘さん:
「地球深部探査船『ちきゅう』の特徴は、後ろにある大きな掘削やぐらです。高さがおよそ130メートルあって、30階建てくらいのビルに相当します」

「ちきゅう」には、日本科学未来館の科学コミュニケーターで、元tbcアナウンサーの三浦菜摘さんが乗船し広報活動に携わっています。
日本科学未来館科学コミュニケーター 三浦菜摘さん:
「13年前の地震について、明らかになっていないことがまだあるんだということを私自身も驚きましたし、それを今もなお研究を続けている方が、こんなにもたくさんいるんだと感じました」

こうした調査は震災翌年の2012年以来12年ぶりで、12月中旬まで続けられます。断層に含まれる物質や力のかかり方がどう変化しているのかなど、次の巨大地震のリスクを調べるということです。