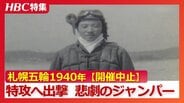断層に並行して走る通勤電車

西日本鉄道(西鉄)は、郊外と福岡市中心部を結ぶ「天神大牟田線」を運行する。全国でも屈指の混雑率のこの通勤電車は、奇しくも断層帯とほぼ並行して走っている。17年前に福岡県西方沖地震が起きてからというもの “次”に向けた対策を最重要課題に据えたのは必然だった。
西鉄・小栁賢史線路担当係長「おそれているのは高架橋の柱がまっぷたつに切れてしまい橋が倒壊することです。そうならないように補強を進めています」
すでに高架の8割の柱を新たに鉄で囲って鉄筋の拘束力を強め、震度7程度の地震に耐えられるようした。残りの補強もできるだけ早く済ませる考えだ。
条例で耐震性能をさらに引き上げ、コスト負担課題に

福岡市は法律の一歩先を行こうとしている。市が保有する建物の耐震化はほぼ終わり、民間住宅も92.1%が耐震化済み(2021年度推計)となったため、次の手は「条例」の制定だった。
福岡市は地域ごとに国が定める「地震地域係数」に着目した。過去の地震記録や被害状況に応じて0.7~1.0の幅がある。1.0が最もリスクが高く、関東や東南海地方が該当する。それより係数が低い地域は、柱の太さや鉄筋の数などで決まる設計地震力が割り引かれ、耐震性能を低減できる。
実は「日本一危ない断層」の直上にあるはずの福岡市の係数は0.8と低く設定されている。最初に決められた1952年の係数がほぼそのまま使われていることや関東や東南海地方との相対評価であることが影響している。
そこで福岡市は、係数を最高水準の1.0まで引き上げる努力規定を全国で初めて条例化した。対象は警固断層帯の上に新たに建てられる中高層の建物や容積率が600%を超える市の中心部だ。 これまで482棟にこの努力義務が課された。しかし、実際に“努力”して係数1.0の基準を満たしたのは124棟で、全体の4分の1ほどに留まっているのが現実だ。

福岡市建築物安全推進課・樗木正武課長「耐震性能を上げるためには、建築時のコストも上がるので、強制的にそれをさせるのもなかなか難しい」
福岡市はパンフレットを配り周知に努めているものの、実効性の担保が課題になっている。