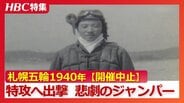本当に怖いのは“未調査”の断層 リスク不明で対策も手つかず

いつ再びマグニチュード7を超える地震を引き起こすかわからない“爆弾”の上で暮らす福岡市民は心穏やかではない。ただ、ほかの活断層と比べ「警固断層帯」は比較的よく研究され、その危険性が広く知られている分、備えることはできる。一方で、全国各地には調査が進んでおらず、地震の発生確率や活動間隔が「不明」とされる断層帯が数多く存在する。警固断層帯が“日本一危ない断層”とされているのは、あくまでも調査が進んでいる断層の中での話しだ。

政府の地震本部がまとめた資料によると、内陸にあり、マグニチュード7以上の大地震を引き起こすおそれのある断層のみに絞っても48の断層が30年以内の地震発生確率が推定されていない。主なものは、青森県から岩手県にまたがる折爪断層、広島県の筒賀断層、 北海道東部の標津断層帯。首都圏でも千葉県南部の鴨川低地断層帯でマグニチュード7.2程度の地震が起こる可能性があるものの、発生確率は「不明」だ。
断層の調査には何年もかかり、そもそも全国に2000ある活断層をくまなく調べる予算も人的資源もない。また、調査したものの地震周期が明らかにならなかった事例もある。断層のエキスパート宮下室長が懸念するのは、こうした「不明地域」でリスクが顕在化しないためにリスクそのものが過小評価され、対策が後手に回ってしまうことだ。
産業技術総合研究所・宮下室長「台風や水害は頻繁に起こりますが地震のように何千年に1回となると後回しにされがちです。しかし、いつ起こるか分からない以上、台風などと同じように注意して暮らす必要があります」