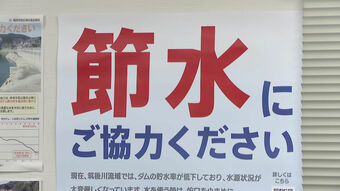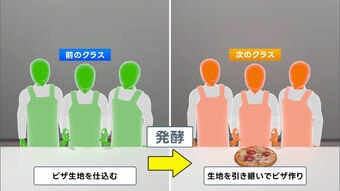「自然保護アピール」だけでない中国の思惑

アジアゾウは絶滅危惧種だ。野生のアジアゾウの生息頭数は世界で約5万頭いるが、象牙を取るための密猟、違法な森林伐採で生息地を追われている。
中国が自然保護に力を入れていることをアピールする目的もあるが、野生のゾウの保護とともに、鉄道の安全運行、さらにいうと、この中国ラオス鉄道が、どのように見られているかについて、神経を尖らせているような気がしてならない。
この鉄道は、ラオスにとっては初めての本格的な鉄道だ。そこを走る車両の製造も、ラオス国内の線路敷設も含め、すべて中国が請け負った。運行システム、安全システムも、ほとんどすべて中国で開発されたものだ。ラオスは中国国内鉄道網に組み込まれたと言っていいほどだ。
総工費約60億ドル(約9000億円)の7割を中国が負担、残りの3割をラオスが負担しているが、そのラオスの負担分の大半は中国からの融資によるものだ。ラオスは中国に対して、借金漬けになって「『債務のわな』に陥るのではないか」と指摘する声が、欧米にはある。
この鉄道は、中国が進める広域経済圏構想「一帯一路」にも関係している。ラオスの首都・ビエンチャンはさらに隣のタイとの国境付近に位置する。だから、ビエンチャンまで鉄道が通じれば、その先はタイの鉄道につながる。
雲南省を中心として、中国全国とラオス、タイ、ベトナム、ミャンマーなど12カ国を結ぶ物流ルートで活用されている。今年6月にはマレーシアの鉄道会社が初めて、タイ、ラオス、そして、この中国ラオス鉄道を経由して中国への貨物列車を運行した。
つまり中国にとって、中国-ラオス鉄道は東南アジアへの重要な物流ルートだ。南シナ海など海路を大回りせずに東南アジアへ陸路による大量輸送を行うことが可能となった。もし、有事となって海上が封鎖された場合、インド洋への出口となるこの鉄道が使える。安全保障上の意味合いもあるわけだ。
一方、海のない内陸国ラオスも、中国に、そしてこの鉄道に依存して経済発展を目指したいと考えている。8月15日には、中国とラオス両国の外務大臣が会談した。ラオスの外務大臣は会談で、中国との関係を「運命共同体」と表現したほどだ。その象徴が、この中国-ラオス鉄道だ。