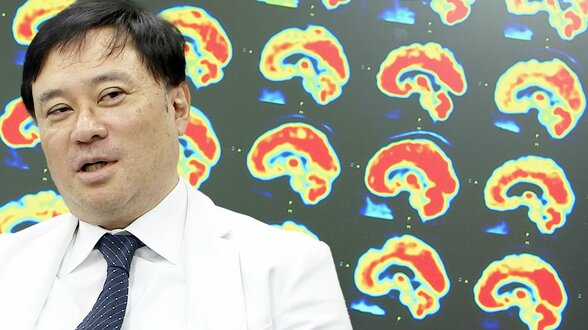■「全数把握」やめる場合…“把握すべき患者”どう線引き?
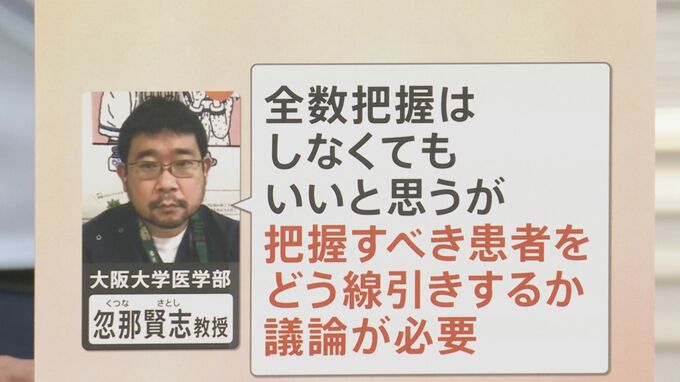
ご出演いただいている大阪大学医学部・忽那賢志教授の意見です。
「全数把握はしなくてもいいと思うが、把握すべき患者をどう線引きするのか議論が必要」というふうにおっしゃってます。
ホラン千秋キャスター:
全数把握の負担をどう考えるのか、その意義をどう考えるのか、どの視点に立つかによって皆さん意見が変わってくるかと思います。忽那先生が議論すべきという“線引”について、どうお考えなんでしょうか?
大阪大学医学部・忽那賢志教授:
全数把握はもちろんできればした方がいいんですけど、現実的にちょっと対応が困難になってきているということだと思います。ですので、全数把握ができなくなってるとしたら、代わりにどうするのかっていうことを検討する時期に来てしまっていると思います。
重症化リスクの高い方に関しては届け出をして、保健所とかの方の目が届くところにいていただいて、必要だったら入院調整をするということ。同時に全数把握をしなくなると、流行状況の把握ができなくなりますので、これまでとは別の方法で流行状況を把握する必要があると思います。それは定点把握とかもそうだと思いますし、例えば検査で陽性の人だけを引っかけるとかですね、何らかの方法で流行を把握する方法をすぐに準備をする必要があるのかなと思います。
ホランキャスター:
理想としては全数把握だけれども、いろんなことを鑑みると定点把握にして、不十分になるところをどのように補うか、皆さんどう考えますかということですね。
大阪大学医学部・忽那賢志教授:
そうですね。そうせざるを得ない状況が今来てしまっているということだと思いますので、次善の策を今からどう構築していくかということなのかと思います。
井上貴博キャスター:
オミクロン株になってから明らかに年齢とか基礎疾患の有無で重症化率にかなり開きが出てきましたよね。ここまで開きが出てくると、インフルエンザ同等の方と、そうではない方、ここを分けるべきなんじゃないかという点はどうお考えですか。
大阪大学医学部・忽那賢志教授:
そういうこともあって今回はその重症化リスクの高い方を、届け出の対象にするということなんだと思います。おっしゃる通り、重症化リスクのない方が重症化することはかなり頻度が低くなってきています。そういう意味では、少しリスクの違いで分けて届け出の対象を変えようということだと思います。
ただし、重症化リスクがない方もですね、まれに重症化してしまうというのがこの病気の怖いところです。そういった方をどう見つけて、医療機関に受診をしていただく方法を作るかということも非常に重要だと思います。
井上キャスター:
「じゃあ明日から全部変えよう」というのはなかなか難しいので、どうグラデーションをつけながら、混乱なく進めていけるかですね。
大阪大学医学部・忽那賢志教授:
そうですね。突然明日から全数把握やめますということになってしまうと、もう明日からの流行状況が全くわからなくなってしまうわけですよね。ですので全数把握をやめるにしても、流行状況が全くわからなくなるというよりは、繋ぎの期間を設けて、ある程度把握しながら、新しい体制に切り替えていくということが大事なんだと思います。