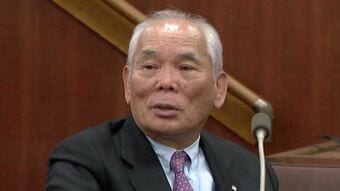兵庫県の斎藤元彦知事による「パワハラ疑惑」を告発した県幹部の男性が死亡した問題について、音楽プロデューサー・松尾潔さんは7月22日に出演した『田畑竜介Grooooow Up』で「今こそ声をあげることを容認する空気を」とコメントした。
スピークアップカルチャーを根付かせるべき
兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑、「疑惑」と一応言っておきますが、限りなくクロに近い音声データなど証拠がたくさん出てきました。斎藤知事に対する見方はもう世の中的にもメディア的にも固まってきている感じがあります。
斎藤知事は限りなく「詰んだ状態」だとジャッジがなされているような、今雪崩を打つような報道になっていませんか? このあたりのメディアの感じは正直気持ち悪くもあります。東京都知事選挙の報道の際、小池百合子さんの学歴詐称疑惑に関する報道も、ちょっと様子を伺うような感じでやっておいて、結局大差をつけてまた選ばれるとパタッと言わなくなったような。
今回は単に、斎藤知事や兵庫県のあり方を話したいわけではなく、皆さんにこれを奇貨として、意識を持ってほしいと思うことがあってこの話題を取り上げました。
今回の悲劇が起きた背景は、内部告発の難しさ、内部告発にかかる「圧」です。告発しようというそのモチベーションに、私情が入っていないことはないと思いますし、個人的な体験に根ざした当事者意識がそうさせていると思うので、公益通報かどうかを分かつ線は限りなくファジーだと思います。
ここでいう「告発」は、刑事訴訟法で定められている「告発」としての効果はないわけで、「それでも言う」のはやっぱり世の中を今より良くしたいという気持ちがあるかどうかというのは問われますよね。
こういうときに声を上げることは、もちろん大切なことだと思います。スピークアップカルチャー、スピークアップ文化という言葉がありますが、亡くなった方の死を無駄にしないためにも、我々は根付かせていくべきじゃないかと思います。少なくとも口をふさぐようなことはあってはなりません。
声を上げることを国全体で容認する空気を
繰り返しになりますが、ジャッジすることは厳しくしなきゃいけないと思うんですよね。特に公益性が高い話では問われることだし、ましてや地方自治体だとより厳格さが求められるのかもしれませんが、民間でも同じことが言えますよね。
公益通報者保護法が2022年6月に改正されましたが、まだ根付いていない企業が多いそうです。基本的に301人以上の労働者を抱えた事業者は内部通報に適切に対応するための整備義務=体制を整える義務が課されました。
一方、300人以下の場合は努力義務です。「いや、うちの会社300人もいないよ」という声も聞こえてきそうです。となると、やっぱり小さな組織では声を上げにくいのかとなってしまいますが、必要なのは「今ある法律が全て」と思わずに、より我々が声を上げてベターなものに改めていくことだと思うし、時代の足音として、まずは声を上げるということを国全体で容認するような空気を今このタイミングで作っていかないといけません。
鹿児島県警の問題のように、官公庁のことで声を上げると否応なく踏み込まれてしまうということが相次ぐと、ますます物騒な時代に向かっているのかなと思ってしまいます。委縮することなく声を上げていきましょう。