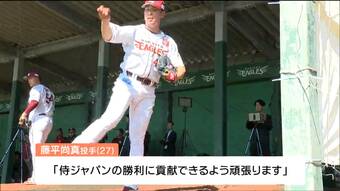7月19日から夏休みに入る小学生も多いことと思います。
そこで気象予報士として自由研究におすすめなのが「夏休み中に雲を全種類見つけてみよう!」というものです。
毎日見える雲の形は違っていて、完全に同じ形の雲は一つとしてありませんが、世界気象機関(WMO)は見える高さや形状などから10種類に分類しています。
ここでは10種類の雲の特徴を写真と共に解説します。
●巻雲(けんうん)

空の高いところ(高度5~13キロ)に現れる、はけで描いたような雲。
「筋雲(すじぐも)」と呼ばれ、秋によく見られる。
●巻層雲(けんそううん)

空の高いところ(高度5~13キロ)に現れる、薄い雲。
「薄雲(うすぐも)」と呼ばれ、太陽の光をさえぎることはない。
太陽の周りに「日がさ」と呼ばれる、明るい輪っかのような模様をつくることがある。
これが現れると、天気が「下り坂」のサイン。
●巻積雲(けんせきうん)

空の高いところ(高度5~13キロ)に現れる、魚の「うろこ」のように小さなかたまりがたくさん集まった雲。
「うろこぐも」や「さばぐも」、「いわしぐも」と呼ばれ、これも秋によく見られる。
●高積雲(こうせきうん)

空の中くらいの高さ(高度2~7キロ)に現れる、巻積雲よりもう少し大きなかたまりがたくさん集まった雲で「ひつじぐも」と呼ばれる。
手を伸ばして、雲の一つのかたまりが指先に隠れれば巻積雲、はみだせば高積雲といわれる。
●高層雲(こうそううん)

空の中くらい(高度2~7キロ)の高さに現れる、空一面に広がる雲。
太陽の光がかなり弱められ、ぼんやり見えることから「おぼろぐも」と呼ばれる。これが現れると、雨が近いことが多い。