取材を終えて
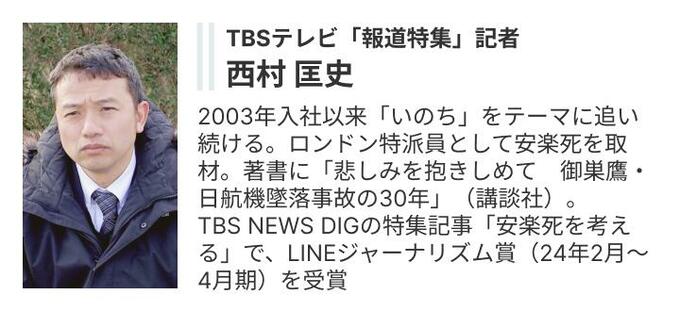
迎田さんが旅立ってから1年7か月が経った。亡くなってからこれまでに、私は1日たりとも、彼女のことを考えなかった日はない。彼女の選択、そして、彼女の人生そのものが、今も私に強烈な印象を残しているからだ。
初めて迎田さんにメールをもらってから1年間、イギリスと日本の間でのzoomのやりとり、東京、ジュネーブ、バーゼルでも時が過ぎるのを忘れて、語り合ったことを思い出す。
安楽死を選択する思いや、病気のことなど、心がふさぐ話も多かったが、それだけではない。彼女のこれまでの恋愛話や、ヨーロッパ各国を旅し、暮らした、心が弾むような話題の方がむしろ多かった気がする。
「本当に幸せな人生だった」。繰り返し語ったその言葉は、彼女がたった一人で人生を切り拓いてきた「誇り」だったように思う。
安楽死の法制化を望んだ迎田さんだが、安易に安楽死を選択することには強く反対していた。
「難病だから誰でも安楽死をしていいというわけではない。基本は生きることだから。やむを得ないときに安楽死がある。そこのジャッジをしっかりしないといけない」
安楽死当日、最後に私は、安楽死を思いとどまることができないかを、あらためて尋ねた。
「あなたは死が差し迫っているわけではないし、まだ生きられると思うんです。介護施設などでサポートを受けることもできますし、もう少し生きてみることはできないでしょうか」
「誰かに頼って生きるなんて嫌なのよ」
その澄んだ瞳を見て、私は彼女の中で生きる選択肢が、わずかにでも残されていないことを悟った。
過酷な幼少期を経て、その後も度重なる困難にぶつかろうとも、自身の力で人生を切り拓いてきた彼女を、私は心から尊敬している。
ただ、同時に、こうも思う。
「誰かに甘えてでも、生きてもらいたかった」

















