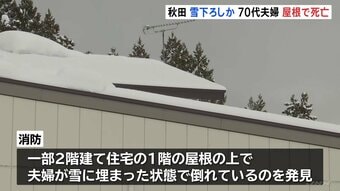「入植するとき条件付きみたいな形で」“非開門”求める裁判を要請した団体
なぜ、国は開門調査を拒むのか。
2008年、国は開けない理由として「防災機能への悪影響」や「農地の塩害」などを挙げていた。(国会議員の質問状に対する農水省の回答)
改めて農水省に取材を試みると、文書で回答を得た。

この中で、2010年の開門を命じる確定判決に従うべく努力をしたが、「地元関係者の理解と協力が得られなかった」と地元の反対をその理由にあげている。(2024年4月の回答)
諫早湾干拓事業で生まれた広大な農地。干拓地を管理する長崎県農業振興公社が5年ごとに契約を更新するリース方式で営農者に貸している。
勝田考政さんは、諫早湾の干拓地に最初に入植した営農者のひとり。門を開けないように営農者が求めた裁判の原告になったが、それは長崎県農業振興公社の要請だったと言う。

干拓地で農業をしていた 勝田考政さん
「僕らは巻き込まれた形ですもんね、完全に。入植する時に条件つきみたいな形で、ここに名前を書けと。裁判で勝たんと、ここで農業はできないんだと説明があって、とりあえずみんな書いて。そこから、ろくな説明もなく、裁判のあの紙に書かされてという形だったんですよね、最初」
原告になることを条件に入植した干拓地。「優良農地」という触れ込みだったが、実際は違ったという。

勝田考政さん
「(2008年の入植当時)ずっと石拾いしてましたよ。貝殻も落ちてるし、トラクターで耕作すると漁網もいっぱい出てきたし、優良地でもなんでもなかったですね。全然意図した経営は出来てないですし、収量は全然取れなかったですね」
この地で農業をするため、年間500万円近いリース料を払い、結果的に2億円近い投資を行ったが、入植して10年目、一方的にリース契約を打ち切られ、農地から追い出されたという。
勝田考政さん
「書類の不備とか、審査に通すことができませんとか、一方的ですよね。文句を言ったら、紙一枚で出て行けとすぐ言われます。そういったところも皆さん怖くて言い出せないと思う。やはり悪質ですね」
勝田さんを含め、干拓地で営農が開始された2008年に入植した営農者の4割がすでに撤退している。
また、国はイサカンの防災効果をうたうが、この潮受け堤防は海からの高潮にしか効果がない。
イサカンを公共事業の観点から研究してきた宮入興一さん。

長崎大学 宮入興一 名誉教授
「河口に巨大な調整池を設けて、水害対策をやっているところは全国にひとつもないです。つまり口実なんですよ。ここでは非常に大きな事実誤認と、僕に言わせればフェイク情報じゃないかと。これを絶えず、農水省も、国も、県も、垂れ流している。
国の方は、この事業が日本の公共事業史の中でも、ほとんど“横綱格の失敗事業”であるというふうなことだと思うんですよ。そのことを暴露されたくないと」