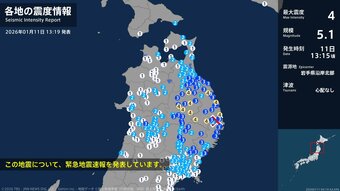米の価格高騰 担い手に課題も
小川彩佳キャスター:
大変な状況は、猛暑やインバウンドが影響しているということを考えると今年だけなのかなと感じますが、長期的な対策も必要になってきそうですよね。
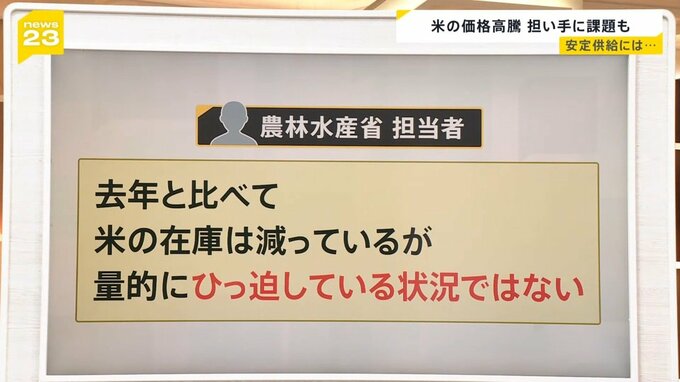
藤森祥平キャスター:
農林水産省の担当者は「去年に比べて米の在庫が減っているが、量的にひっ迫している状況ではない」としています。
これから新米が本格的に出回る季節でもありますから、私達も慌てることなく必要な量だけありがたくいただきましょう。
小川キャスター:
今すぐスーパーに行かなければならないという状況ではないということですね。
猛暑の影響で、一部の産地で収穫量が減少しているという話がありましたが、対策もしていて、暑さに強いお米の導入も進んでいるんですよね。
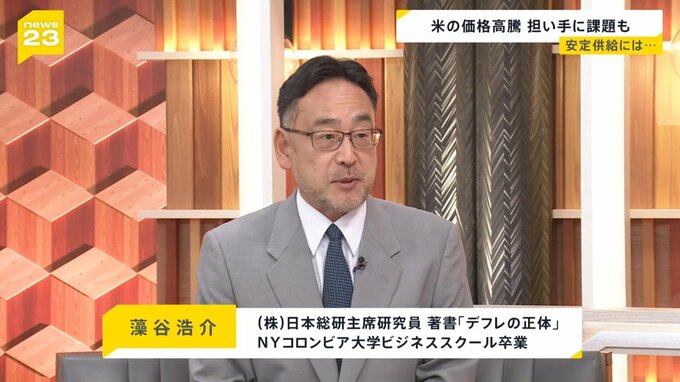
日本総研首席研究員 藻谷浩介さん:
温暖化で北海道のお米が美味しくなったのは有名ですが、九州がダメになったか?というと、九州のお米も品種改良が進み、引き続き全国トップクラスのお米を作り始めています。
これ以外に値上がりの要因が2つあると思います。
1つめは、円安です。
お米は100%自給しているので、円安は関係ないのでは?と思いますが、お米を栽培するのに必要な肥料の原料は全量輸入ですし、農機具を使ったり農薬を作るのに使う油も全量輸入しています。
ですから、円安で輸入代が上がっているので農産物の価格が上がる。円安だから競争力が高くなるとはなっていない。もっと減肥料・減農薬を進めて、輸入の石油に頼る分を減らさなくてはいけない。
あともう1つ、お米は安いんです。
ご飯ジャー1杯で十何円だし、今は多分、20円ぐらい。パンだったら1個100円とかしますよね。つまり安いのが当たり前で、みんなが「高くなる」というけれど、こんなに美味しいのに安すぎて生産者が全く儲かっていない。
ですから、作る人を増やすためにも、ある程度長期的に値上がりするのは避けられないと思います。1本百何十円の水とか、パン1個、パスタに比べて決して「高い」とは言えないのではないでしょうか?
========
<プロフィール>
藻谷浩介さん
(株)日本総研主席研究員 著書「デフレの正体」
NYコロンビア大学ビジネススクール卒業