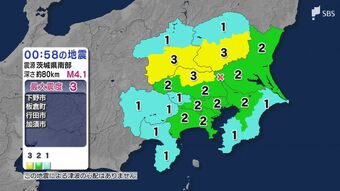1000年近く変わっていない京都の「アクセント」

偉大な功績から絶対的な存在だった金田一にも臆せず、挑んでいた山口の姿勢は、旧新居町という「地方」に住み続け、研究したことに根差しているようだ。
金田一は、平安時代末期の文献研究からその時代の平安京のアクセントと現代の京都のアクセントがほとんど違わないことを自ら解き明かしている。つまり、京都のアクセントは、少なくとも千年近く大きくは変わっていないということだ。なのに、「無型アクセント」へ至る想定では、地方でアクセントはどんどん変わることになっている。
ここに、山口は強い抵抗を示した。都会に住む者はしっかりアクセントを守り、地方では、言葉に対する規範意識が低いので、どんどんアクセントが単純化すると見立てる金田一説は地方を軽く見ていやしないか、と。岸江教授は、その視座こそが「山口流の本質」だと語る。
いまから20年あまり前に、山口が「無型アクセント」が日本語の祖型ではないか、という著書を出し、学術誌上で論争も起きた。岸江教授は、現代のアクセント分布の成立過程に、独自の推論を加えながらも「無型アクセントは古いと思う」と“山口説”の起点を支持する。
しかし、現状、学界全体としては「山口説を支持する研究者も結構いるが、定説にはなっていない(岸江教授)」。日本各地のアクセントがどのように成立したかについて、確定的な全貌は、いまもつかめていないのだ。(文中敬称略)
(SBSアナウンサー 野路毅彦)