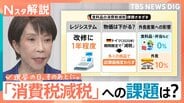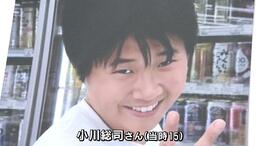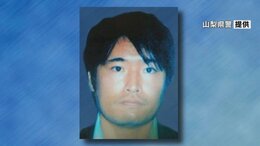基地の広大な土地とインフラ 都市の再構成に「不幸中の幸い」
復帰前にはすでに、沖縄の米軍基地は発展の阻害要因と考えられるようになっていた。しかし大規模な返還が望まれたのには、違った側面もあった。基地の内部に残る、返還後も活用できそうなインフラや建物などは、できるなら活用したいという期待があったこともうかがえるのだ。
例えば、転用計画図で嘉手納基地の一部は「保留区域」を示す黒線で囲われた。早期返還の期待値は低いとされていたが、将来計画として、空港機能は残し、滑走路に隣接する区域を工業地域化することを示す水色が塗られていた。
▽翁長巳酉さん
「嘉手納はちょっと動かないかもという前提で、こういうふうにしたらいいかな、ってことですね。でも当然と思っていたんじゃないですか」
▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」
「これらの基地が、都市再編成上重要な地点に相当の広がりと膨大な施設の集積地をもって配されていることは、不幸中の幸い」
「再編成を行うには軍用地の存在は非常に有利な要素でもある」
こうした考え方のもとで、米軍基地の大規模返還後の利用計画の基本方針が掲げられた。
【軍用地及び軍用施設転用の “基本方針” 】
〇中核都市圏を、有機的に結合(大那覇市、沖縄市)
〇那覇市は雑居的性格を改め、商業的中心部として整備、行政機能は新たな地域へ移す
〇宜野湾市、北谷村(現在の北谷町)は膨大な施設を有効に活用する(国際会議施設など)
県土の大規模な再編成に、個々の地主の利害関係は必ず生じる。そうした調整にも県など行政が指導力を発揮する必要性をみとめたほか、地主の利益を守りながら事業を進める「軍用地転用・開発機構(仮称)」という事業主体の設置まで提案した。
これほど大きく描かれた夢の中心にあったのは「鉄道構想」だった。