4期連続最終赤字の先にある 上場の意味とは!?
日本経済新聞の編集委員で、流通業界に詳しい中村直文氏に、今回の上場の意味を聞いた。

日本経済新聞社 編集委員 中村直文氏:
イトーヨーカ堂という収益が低下してきてしまった事業部門をさらにリストラして解体していく風にも見える。身売りできないから異形のカタチになったのが正しい言い方。切ってしまえばそれで済む話。切れないから、少しややこしいスキームになった。時間をかけた解体劇がいよいよ最終ゴールになりつつあるのが今の現実。
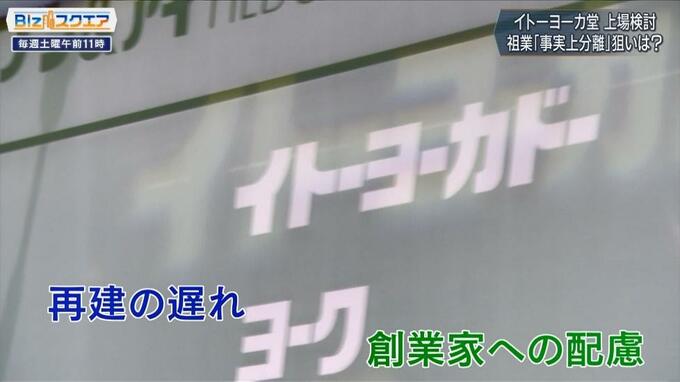
中村氏は、スーパー事業を事実上分離する背景に、再建の遅れと、創業経営の配慮を指摘。
日本経済新聞社 編集委員 中村直文氏:
長年イトーヨーカ堂が再建できないままにズルズルと業績が低下していった。企業価値が低下していく中で売るに売れなくなってしまった。もう1つは元々親会社。基本的に祖業だから売らないわけじゃないといっているが、現実的にいうと、歴史的な存在でもあるし、人的な繋がりがあり、なかなか切るに切れない事業だったと。

新たな資本政策で再建は進むのだろうか。
日本経済新聞社 編集委員 中村直文氏:
チェーンビジネスは一旦売り上げが落ちると、なかなか回復できない。またリストラする、そうすると競争力落ちる、またリストラしていくという形で、どんどんジリ貧になっていくというモデル。ここ10年以上、イトーヨーカ堂は(ビジネスとしての)賞味期限切れてるのにもかかわらず、大きな対策ができなかった。

セブン&アイは今後、グループの稼ぎ頭であるコンビニ事業への集中をさらに進める考えだ。
日本経済新聞社 編集委員 中村直文氏:
これから厳しい競争を戦うためにはコンビニに集中していくしかない。市場の圧力もそうなっているから、イトーヨーカ堂を決して捨てるわけではないが、切るに切れないヨーカ堂をどういう形で立て直すか。そこにセブン&アイの苦しさがあると思う。














