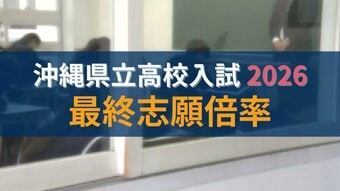遺族以外の参列者にも“オープンに” 慰霊祭を引き継ぐ思い
遺族・又吉弘子さん
「(今後)どうなるんだろうと思いはするね、だんだん高齢化すると。しかも(ガマへは)歩ける人じゃないと来られないしね。きょうもちょっとお祈りしてきた。どうか私の足腰を元気にしてくださいって。私が元気なうちは来ますから。せめて」
こうしたなか、参列者の顔ぶれに変化が。読谷村役場の平和ガイドとして働き、チビチリガマも案内する青山さんと又吉さん。3年ほど前から、参列するようになりました。
ガマの中で 青山さんと又吉さん
「灯油をまいて火を出したところは黒くなってるのかな」「たぶんススで黒くなっている」「この辺とか」
読谷村地域ガイド「絆会」 又吉スガ子さん
「やっぱりお線香の煙でも、ちょっと目にくるね。(当時は)もっと煙で大変だったでしょうねと話をしていた」
読谷村地域ガイド「絆会」 青山礼子さん
「私たちは遺族でもなく、体験者でもない。(チビチリガマの悲劇を)話すことにものすごくためらいがあって、葛藤がありました。何度もやめようと思った。でも、ここにきて初めて、この空気感とか色とか知ることが出来た」
参列しなければわからなかったことは、他にもー
遺族・與那覇徳市さん
「(両親を失った母は)苦しかったかね。私は小さかったから、なぜ母がここで泣くかが分からなかったわけ。あぁ、お母さん、話せなかったんだね。今だったら分かるわけ」
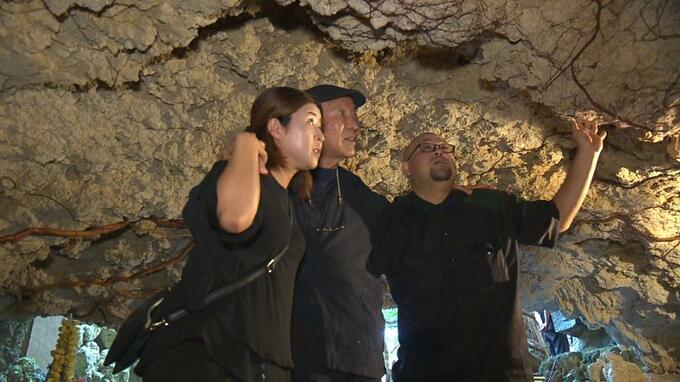
青山礼子さん
「一番嬉しいのはこうやって慰霊祭に来て、関係者の方の生の声が聴けるのが、私たちには最高の学びになる」
読谷村職員労働組合の青年部でも、代々参列する伝統をつないでいます。
4月から読谷村役場職員 玉城源弥さん
「チビチリガマは暑いなと。すごく当時の人も暑かったのかなという感じがした。(先輩たちが)ずっとつなげてくれているので、自分たちもつなげていけるようにしていきたい」
チビチリガマ遺族会 與那覇徳雄会長
「10年前から(慰霊祭を)オープンにしながら、チビチリガマとはどういう所だったのか年に1回は見てもらおうと。私たちが望むのは、このチビチリガマから平和を発信していくこと。ぜひ慰霊祭を続けていけるように頑張りたい」