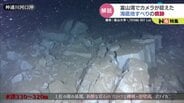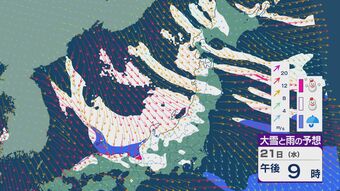地震による津波でも大きな被害を受けた石川県珠洲市ですが、ある地区の住民は全員が避難し命を守りました。日ごろからの防災対策と地域の合言葉が大きな役割を果たしました。

記者
「珠洲市の寺家地区です。住宅の1階部分が突き抜け、ガレージは海の方に押し出されていて津波の恐ろしさを物語っています」

石川県珠洲市三崎町寺家の下出地区。
海沿いに民家が集まり35世帯、80人ほどが暮らすこの地区では、地震発生から間もなく津波が押し寄せ、住宅などに大きな被害の爪痕が残りました。

下出地区区長 出村正広さん
「潮が引き始めた。ダーッと灯台の向こうくらいまで潮が引いて、引いたからこれで終わりかなくらいに簡単に思っていたら、次またどーっと押し寄せてきて、今度はひとつじゃなかった。こんな高い波じゃなかったけど、次から次に折り重なるみたいな感じで」

被害は大きかったものの当時、地区にいた全員が海抜23メートルの高台にある集会場に避難して無事でした。

下出地区では、東日本大震災での津波被害を大きな教訓にして自主防災組織を立ち上げ、地震発生時の避難方法を確認。高台の集会場へ逃げる階段の整備を進め、毎年、避難訓練を重ねて、住民に揺れが来たらすぐに避難するとの習慣づけをし、防災への意識を高めてきました。

下出地区区長 出村正広さん
「『なんかあったら集会所』という合言葉をみんなで話し合いながら、そういう言葉を作って、なるべく早く集会所へ上がるような話はしていた」

「何かあったら集会場」
須須神社の参拝客なども含めて180人ほどが地震があってから5分以内に避難できたということです。

奥浜敏孝さん
「私の嫁さんがもうパニック状態で『あー!』って言ってたから『落ち着け、落ち着け』って言ったが、こんなでかい地震なら津波は来るなあと思って、2人してその階段を2回目の地震が終わってからすぐ上がってきた」
家が全壊した新田久江さん
「『あっ、これは津波だね』って。みんな大体そんなの分かるから集まって来て、一緒に来たらもう何人もいた。訓練したお陰で皆さん集まってくれた」

住民のほとんどは高齢者で、壊れた家屋の片付けは危険な状態のため、はかどってはいませんが、仮設住宅への入居を待ちながら住み慣れた地区の復興に希望をつないでいます。