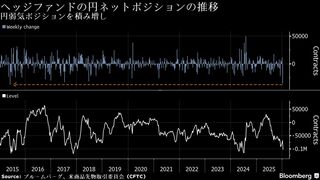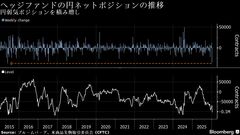(ブルームバーグ):17日の日本市場では債券が下落(金利は上昇)、超長期債利回りが大幅に上昇した。政府の経済対策に伴い財政悪化懸念が浮上した。株式は下げ渋って取引を終え、円は対ドルで下落した。
債券市場で新発20年国債利回りが一時2.75%に上昇、1999年以来の水準を更新した。日本政府の経済対策規模は17兆円台との報道を受けて国債増発への懸念が広がった。10年国債利回りも17年ぶりの水準を連日で更新した。日経平均株価は日中の緊張を受けて一時1%超安で節目の5万円を割り込んだ後、小幅安まで下げ幅を縮めた。円は対ドルでニューヨーク終値比でやや下落している。

日本の実質国内総生産(GDP、7-9月期速報)は6四半期ぶりにマイナスとなり、経済対策の規模拡大を後押しする要因となる。これは日本銀行にとって利上げを抑制する方向に働く一方、米政府機関閉鎖の終了を受けて経済指標が出始めることは金融政策判断への根拠が増えることになる。金融市場は各種要因と政策への複雑な影響を予想することになる。
みずほ証券の松尾勇佑シニアマーケットエコノミストは17日付リポートで経済対策について、高市政権の積極財政の期待感を維持する規模感で検討されているみていると指摘した。その上で与野党との調整次第で規模が変わり得る点に留意しておきたいと付け加え、円安進行で日銀が12月利上げに追い込まれる展開も十分に想定されるとした。
債券
債券相場は下落。米国の長期金利が上昇した流れを引き継いだ上、政府が近く策定する経済対策の規模が17兆円台になるとの報道を受け国債増発への懸念から売りが出た。
新発20年国債利回りは一時2.75%と1999年以来の高水準を付けた。19日の入札に対する警戒感も出ている。10年債や30年、40年債利回りも上昇が大きくなり、利回り曲線はスティープ(傾斜)化した。
岡三証券の長谷川直也チーフ債券ストラテジストは、政府の経済対策規模が投資家に警戒されており、不透明感から年限の長いところに売り圧力がかかっていると指摘。「長期金利の1.7%台は需要があるものの、恐る恐る慎重に買っていくことにならざるを得ない」と述べた。
財務省が17日実施した10年物価連動債入札の結果によると、最低落札価格は99円00銭と、市場予想98円80銭を上回った。投資家需要の強弱を反映する応札倍率は3.46倍と、前回8月入札の2.92倍から上昇した。
新発国債利回り(午後3時時点)
株式
東京株式相場は続落。日経平均株価は一時5万円を割り込んだが、下げ渋った。日中関係の緊張懸念からファーストリテイリングやオリエンタルランドなど小売りや陸運、空運をはじめとするインバウンド関連、中国関連株に売りが優勢となった。自動車やゴム製品株など景気敏感株の一角も軟調。
半面、先週末の米国株市場がテクノロジー株中心に底堅さを示したことが好感され、半導体や人工知能(AI)関連の一角は堅調。シティグループ証券が目標株価を引き上げたキオクシアホールディングスが大幅高になった。金利高を背景に銀行や保険などの金融株も底堅かった。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平上席投資戦略研究員は「リスクオフではなく、物色が循環する中で、 個別材料を受けた物色になっている。全体としては方向感がない」と述べた。
日中関係に関しては、インバウンドのコト消費では中国観光客依存が緩和されたものの、モノ消費では中国観光客依存が続いている面がいまだにあるとして「モノを売る系のインバウンド関連にはそれなりに影響が出るとの認識になっている」との見方を示した。
パラソル総研の倉持靖彦副社長は、金融株に関して株主還元を継続的に行う可能性がある点や、財政リスクや日銀による利上げで金利が上昇しやすく「手掛けやすい」と指摘。12カ月先株価収益率(PER)では割安感もあり、ハイテク株からのローテーションの中で物色されやすいと話した。
為替
円相場は対ドルで154円台後半に下落。政府の経済対策規模の拡大観測から財政悪化を懸念した円売りが優勢だ。7-9月期の実質国内総生産が6四半期ぶりのマイナス成長となったことで、日銀の早期利上げ観測の後退も円の重しになっている。
三井住友銀行の鈴木浩史チーフ・為替ストラテジストは為替相場について、高市政権の財政への期待感もあり円安圧力が根強いと述べた。米株が先週下げるような場面では若干円高に進むこともあったとして、ドル・円が155円を抜けるには距離あると述べた。
今週から米国の経済指標の公表があり、エヌビディアの決算も控えて注目が集まるとしている。
この記事は一部にブルームバーグ・オートメーションを利用しています。
--取材協力:長谷川敏郎.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.