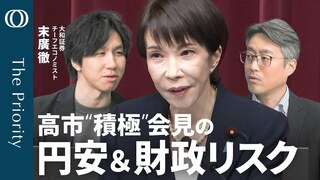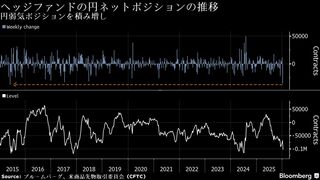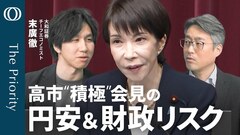(ブルームバーグ):こんにちは。谷口崇子です。今月のニュースレターをお送りします。
芸術の秋に、アートの記事を一つ。発端は約1年半前にさかのぼります。現代アートに詳しい友人から「とんでもなくぜいたくな美術館がある」と誘いを受け、今は閉館したDIC川村記念美術館(千葉県佐倉市)に小さなグループで出掛けたことでした。
都心からのアクセスが不便で、その日も入館者はまばら。一通り見て回った後は、青い芝生の広場で持参したお弁当を広げます。子供たちが駆け回る中、一目でそれと分かる丸みを帯びたヘンリー・ムーアの彫刻作品が鎮座しており、そこが美術館であることを実感させてくれました。
しばらくして、運営元の化学メーカーDICが美術館の休館を決めた時、ショックより「まあそうだよな」という諦めの気持ちが先に立ちました。
ぜいたくな鑑賞体験を味わった誰もが気付くことですが、入館料1800円で運営費が賄えそうにないのは明らかでした。事実、ずっとDICの持ち出しが続いていました。アクティビスト株主は「客より警備員の数の方が多い」と批判しました。
資本の論理と文化的価値を重んじる立場はどちらも間違っていませんが、交わることもなさそうです。創業家が会社の資金で大量の美術品を購入することは、今の常識からはかけ離れているように思います。ムーアの彫刻は17日、競売にかけられます。新しい持ち主の心を満たしてくれることを願っています。
海を渡るモネの「睡蓮」
化学メーカーでありながら大量の美術品を保有していることがアクティビスト株主に批判されていたDICの美術品売却手続きが始まる。まず、英競売大手クリスティーズが米ニューヨークで現地時間17日夜に開催する国際オークションで、特に価値の高い8作品が競売にかけられる。
クリスティーズによると、8作品が出品されるのは、印象派を含むモダンからポストモダン期の作品を含む20世紀美術のうち、特に高額な傑作が集まる「20世紀イブニング・セール」。同社は毎年11月にニューヨークで大規模なオークション週間を開催しており、DICは今回、8作品を含む20作品程度を出品した。残りはその他の日中のセールなどに回る。
主要8作品のうち、特に注目を集めているのは、クロード・モネの「睡蓮」(1907年)だ。推定落札価格は4000万-6000万ドル(約62億-93億円)と、クリスティーズが同イブニング・セールに出品予定として公開している62点の中でも2番目以下の倍以上とずばぬけて高い。ただ、1点だけ推定価格が公表されていないデイヴィッド・ホックニーの作品は過去に超高額落札の実績があり、モネの作品は今期の最高額にならない可能性はある。
「モネの市場価値は近年、ますます高まっている」。クリスティーズ印象派・近代美術部門のシアン・チャトコウ副会長は、ブルームバーグの取材にこう指摘する。
印象派の名前の由来となった作品「印象、日の出」や睡蓮の連作で知られるモネについて、「印象派の中心的存在として、同時代の画家たちよりも長きにわたって成功を収め、その後に続く何世代もの芸術家に影響を与えた」と評価する。
推定価格の根拠については、同じ1907年に描かれ、2022年に3670万ドルで落札された「睡蓮、灰色の時」を比較対象に挙げた。
DICの所蔵作品は「より豊かな色彩、躍動的な筆致で反射する陽光を輝かしく描いている。その卓越した品質と鮮烈さから、さらに幅広い愛好家の関心を得られると判断した」とコメントした。
「売らない」方針を一転
睡蓮はDICにとっても特別な作品だった。同社は所有する384点の美術作品の約4分の3を売却する方針だが、池田尚志社長は3月の記者会見で、同社コレクションの象徴的存在である20世紀現代美術の巨匠、マーク・ロスコの絵画7点などと共に睡蓮を売却せずに残す意向を示していた。
一転、売却を決めた理由について、同社広報担当者は、睡蓮を「当社保有作品を代表する作品の一つだと認識している」としつつ、事業会社としての責任、美術品を保有する者としての責任に向き合った上で、今後残す作品を戦後の米国美術を中心とした20世紀美術作品と再定義。踏み込んだ検討を重ねた結果、継続保有対象から外れたと説明した。売却圧力を強める株主側の主張に歩み寄った結果とも言える。
イブニング・セールに出品する8点の推定価格の合計は7020万-1億380万ドル(108億-160億円)で、213億円だったDICの前期(24年12月期)の純利益の規模を考えると相応に大きな水準。DICは第一弾となる20点程度の売却で25年中に約100億円のキャッシュインを目指している。
競売は結果の予測が難しく、現時点では今期の業績予想に織り込んでいない。25年12月期の年間配当予想は1株当たり200円(前期は同100円)と増配としているが、美術品売却などで追加収入があった場合は機動的な株主還元を行うとしている。

クリスティーズは、DICのコレクションを「長い間市場に出ていなかった作品群」と紹介している。チャトコウ氏は、美術館などの公益性の高い機関が長期間保有を続けた作品は「それだけ貴重な作品だという証拠で、さらに人気が高まる」と説明する。
今回の睡蓮を購入できる機会は、1985年にDICが米競売大手のサザビーズで落札して以来、40年ぶりだ。チャトコウ氏は「このレベルの作品を持ちたいと熱望する世界中のコレクターから強い関心が寄せられる」とみている。
「最も高価な瞑想室」
DICの2位株主で香港のヘッジファンド、オアシス・マネジメントのセス・フィッシャー最高投資責任者(CIO)は、売却手続きを開始したのは「素晴らしい決断」と評価した上で、 美術品は主要事業と無関係で総資産利益率(ROA)を押し下げており、全作品を売却するべきだとの認識を示した。
DICは3月に佐倉市の美術館を閉館。2030年以降に縮小・移転して東京都港区六本木で営業を再開する計画だ。フィッシャー氏は残ったロスコ作品などのために新たな美術館を建設することに「強く反対する」と強調。「最も高価な瞑想(めいそう)室を造るようなもので、企業の資産の使い方として不適切だ」と非難した。
DICの池田社長は「約100点の保有を継続することに変更はない」とした上で、40年以上にわたる美術館運営を通して得た、芸術と美術に対して「真正性」と「信頼性」を持つ企業イメージは「容易に置き換えられるものではない」と反論。今後、新たな美術館を起点に公益活動の幅を広げつつ、その意義をステークホルダーに丁寧に説明し、理解を深めていきたいと説明した。
国立美術館の運営を経済的観点を含めて評価する有識者会合メンバーでもあるピクテ・ジャパンの大槻奈那シニア・フェローは「文化財の散逸を防ぐのは国の役目だという側面もあるが、現実に日本の公立美術館の収蔵庫の収容スペースは限界に近い」と指摘。一方で、上場企業本体による美術品保有は、資産の効率性の観点で取締役会で厳しい議論があってしかるべきだとも話す。
その上で、民間のコレクションを守るためには「芸術作品のトークナイゼーション(デジタル証券化)が一案では」と提案する。美術館を支援したい個人ファンを念頭に、絵画の所有権や修復プロジェクトの支援権などをトークンとして小口化し発行。保有者は権利を売買でき、特別観覧や限定グッズなどの優待のほか、将来的な収益配分が得られる仕組みだ。
大槻氏は「企業の美術支援は意義深く、民間の力を生かす工夫が必須だ」との見方を示した。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.