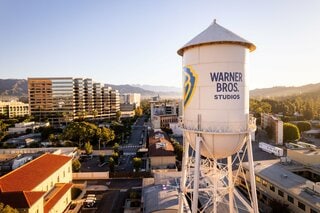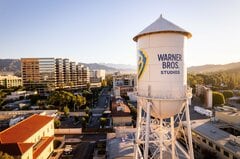(ブルームバーグ):東京には世界屈指の「イケてる」街が幾つもある。
だが、タイムアウト誌が「世界で最もクールな街」として神保町を選んだと聞いたとき、多くの人と同じように思わず眉をひそめた。書店とスキー用品店が立ち並ぶ神保町が、東京一のみならず、世界一とは。
神保町はもちろん、申し分ない街だ。皇居の北東、神田川沿いに位置し、100軒を超える書店と都内屈指のカレー店が並ぶ。職人系カフェと昔ながらの喫茶店が混在し、学生街らしい若々しい雰囲気もある。靖国神社や日本武道館、東京ドームも徒歩圏内だ。
それでも、東京には似たような魅力を持つ地域が他にもある。そもそも最もクールな街とは何を意味するのか。誰がその基準を決めているのか。
東京はこうしたランキングの常連だ。日本の首都に対する世界のイメージが「ブレードランナー」風のネオン高層都市から歩ける街へと変わり始めたのは1990年代末から2000年代初頭にかけてだった。
当時、日本はまだ訪日観光客も少なく、「トレンドを決める条件」とはつまり、書き手自身が誰よりもその街をよく知っているということだった。
こうして、次々と新たな「発見」がなされ、人気が出るたびにトレンドセッターがさらにマイナーな地域へ移っていくというチキンレースが始まった。
かつては下北沢や高円寺、吉祥寺といった、インディーズ音楽や個性的な店が並ぶ街が注目された。その後、焦点は代官山や中目黒へ移った。代官山は「リトルブルックリン」とも呼ばれる高級かつしゃれた街だが、正直その呼称には首をかしげる。
中目黒も人気を集めたが、英ボーイズバンド、ワン・ダイレクションのハリー・スタイルズが村上春樹を読みながらそこに住んでいたと報じられたころには、すでにトレンドは変わっていた。
最近では、渋谷近くの緑豊かな富ヶ谷や、にぎやかな三軒茶屋が注目を浴びている。ローカル誌では、蔵前や清澄白河といった東京東部の街を称賛する記事も多い。
何をもって「クール」とするのかは分からないが、共通するのはにぎやか過ぎず、主要な交通拠点に近いものの、その一部ではないことだ。歩きやすく、ローカル感があり、家賃が手頃でコーヒースタンドや古着店、レコードショップが集まることだ。
筆者自身はコーヒー通でもファッショニスタでもオーディオマニアでもないが、そうした街にはアーティストやDJ、モデル志望のような人たちが集まる傾向がある。
高級車を乗り回すほどの富裕層は少なく、かといって本当の庶民層も少ない。そして外国人観光客がバックパックやカーゴパンツ姿で現れ始めたら、もう次の街を探す時期だ。
一方で、「クールではない」街もある。広尾や麻布は居住地として人気だが、日本に赴任するリッチな外国人が多過ぎる。北千住はあまりに生活感が強い。
六本木はかつて流行の最先端とされたが、金融マンやクラブ好きの街にとどまった。お台場や豊洲の埋め立て地がトレンドになるのは、少なくとも数十年先だろう。
上野は庶民的過ぎ、西新宿は無機質過ぎる。原宿もかつては世界的なファッションの中心だったが、今では商業化し過ぎた。
渋谷
渋谷に長年住む身としては、こうしたランキングが観光客を別の地域へ分散させてくれるなら大歓迎だ。
ただし、東京を最もクールな街でひとくくりにすることはできない。魅力はむしろ地域ごとのちぐはぐさにある。
渋谷の面白さは、一本裏通りに入るだけで、雑多なクラブ街や怪しげな店から、経営者や政治家が住む緑豊かな高級住宅地へと一変するところにある。センター街が観光客で混み合っても、ビル上層階にひっそりとある小さなバーや地元の名店に気付く観光客はほとんどいない。
そして何より重要なのは、徒歩数分で富ヶ谷や代々木公園に行けることだ。反対方向へ進めば、代官山の隠れたブティック、青山や表参道の高級ショッピング街、恵比寿のトレンディーなバー、あるいは注目され始めた池尻大橋にも出られる。
こうした多様さこそが東京の魅力であり、移動のしやすさが「人が増えたら次の街へ」と軽やかに動ける自由を生んでいる。
だから「東京で最もクールな街」を決めようとするのはやめた方がいい。そんなものは存在しない。仮にあったとしても、教えるつもりはない。
(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Tokyo’s Coolest Neighborhood? There Isn’t One: Gearoid Reidy(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.