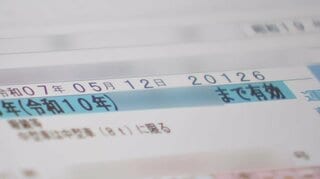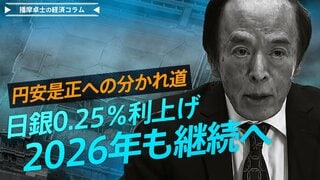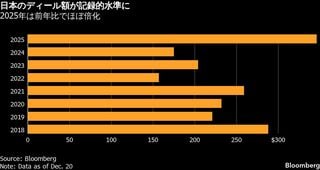(ブルームバーグ):日本銀行の田村直樹審議委員は16日、物価の上振れリスクが膨らむ中、利上げを判断すべき局面に来ているとの認識を示した。沖縄県金融経済懇談会で講演した。
田村氏は、将来の急激な利上げショックを避けるため、「中立金利にもう少し近づけておくべきだ」と指摘。日銀は2%の物価安定目標の実現時期について、展望リポートで示している2027年度までの見通し期間の後半としているが、「実現時期が前倒しとなる可能性も十分にあると考えている」と語った。
政策金利の引き上げが遅れて物価が大きく上振れする「ビハインド・ザ・カーブ」に陥れば急速な利上げを余儀なくされ、日本経済に大きな打撃を与え得ると説明。物価上昇率に比べて金利が低過ぎれば、預金の実質的な目減りが続いてしまうとも主張した。
日銀は前回9月の金融政策決定会合で、5会合連続となる政策維持を決めた。政策委員9人の中で最も利上げに積極的とみられている田村氏は、0.5%程度の政策金利の据え置きに反対し、0.75%程度への利上げを提案した。29、30日の次回会合を控え、利上げの必要性を改めて訴えた。
緩和的でも引き締め的でもない中立金利までに「まだまだ距離がある」としたが、「1%以上のどの辺りかは、政策金利を引き上げつつ経済・物価の反応を見て探っていくしかない」と指摘。早過ぎる金融引き締めによって、経済・物価が共に変動しない状態に戻ることも避けるべきだとの見解を示した。
午後の会見では、午前の講演で言及した目標実現時期の前倒しについて、米関税政策が具体化する前に想定していた2025年度後半に「実現できる可能性も否定できない」と語った。円安に関しては「物価の上振れリスクを増大させる」とし、企業の価格設定行動が積極化する下で、為替変動の影響も注視していく考えを示した。
10月会合で再び利上げを提案するかとの質問には、「現時点で確たることは申し上げられない」と回答した。その時点までの経済・物価情勢や会合での議論次第だとしつつ、「中立金利にもう少し近づけ、上下双方向のリスクに備えるべきだ」と繰り返した。
インフレ
消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)は、3年以上も日銀目標の2%を超えて推移しており、最近は食料品価格の高騰がけん引役となっていた。足元で再び進行する円安も輸入物価を押し上げる可能性がある。
田村氏は、人件費が食料品の値上げ理由となってきていることを踏まえ、「食料品価格は今後も持続的に上昇する可能性が十分にある」と主張。国内物価は、日銀が7月の展望リポートで示した見通しと比べて「上振れて推移するリスクが大きい」とみている。
大きなリスク要因と位置付けられている米関税政策の影響に関しては、海外経済の減速などの影響から「無傷ではいられない」としつつ、「海外経済の減速も当初考えていたほどではない可能性が十分にある」との見方を示した。
9月会合では高田創審議委員も田村氏と同様に0.75%程度への利上げを提案した。日銀内での利上げ議論の高まりを受けて市場で早期利上げ観測が強まったが、足元では日本の政治情勢の混乱などを背景に思惑も後退している。一時、70%程度に高まっていた今月の利上げ予想は足元で10%台となっている。
午後の会見では、政治情勢についてコメントは控えるとしつつ、今後の政権による経済政策が「経済・物価にどのような影響を与えるのかを踏まえて適切に金融政策を判断していきたい」と指摘。物価の安定という使命を果たすために、目標の持続的・安定的な実現を目指して政策運営していくことに尽きると語った。
(午後の記者会見の内容を追加して更新しました)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.