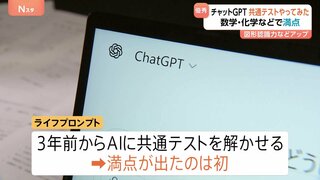4日の自民党総裁選で高市早苗氏が自民党総裁に選出された。
少数与党下で首相に就任するかは不透明な部分が残るが、高市政権が誕生する場合の経済政策への影響などをQ&A形式でまとめた。
Q.経済政策はどのように変わるか?
財政・金融政策についてはハト派。
「責任ある積極財政」を掲げ、必要な施策であれば赤字国債も厭わない姿勢を示す。政府による成長投資を特に重視。
金融政策については、政府と日銀の連携を重視する。財政・金融政策を通じて需要超過の状態を維持することで、投資などによる供給力拡大を促す「高圧経済政策」を志向していると考えられる。
また、給付付き税額控除の導入や所得税の基礎控除引き上げを強調するなど、現役世代・勤労者世帯・中間層家計の支援を重視していることがうかがえる。
最低賃金の引き上げなどを重視してきた岸田政権や石破政権と比べると、「弱い人を守る」よりも「頑張る人が報われる」ように、という理念が強く、この点は徐々に政策でも表面化していくと考えられる。
Q.実際に財政拡張色が強まるか?
総裁選では、財政ハト派色を抑えた印象。
積極財政路線を打ち出しつつも、“最終的に財政健全化も必要”との発信を行っているほか、野党の要求する消費税減税についても距離を置いている。
高市氏の総裁就任を英国のトラス・ショックと重ねる向きも多く、自身の政策が市場の混乱を招いた、と取られるような事態は避けたいのではないか。極端な政策を志向はしないとみている。
Q.金融政策はどうなるか?
大方の市場の見方の通り、10月利上げのハードルは上がったとみられる。しかし一方で、市場の混乱を回避する観点でも日銀に強い圧力はかけにくい。
物価高対策を行う中で、自身の発信が極端な円安を招くことも避けたいだろう。高市氏の経済認識自体も、日銀認識である「基調的インフレ率は2%には達していないが近づいている」と、大きく相違しているわけではないとみられる。
引き締めに慎重な立場や政府と日銀の連携を重視する姿勢を見せつつも、日銀の利上げ方針そのものは容認するのではないか。
金融政策に対するスタンスが現れやすいのは、政策金利が1.00%に到達した後と考えられる。日本銀行の推計する中立金利のレンジに入り、それ移行の利上げは「緩和から中立水準への調整」から「引き締め的かもしれない」領域に入ってくる。1.00%以上への利上げに対しては、牽制が入りやすいだろう。
Q.今年の予算編成や経済対策はどうなるか?
例年通り、秋〜年末にかけて経済対策(補正予算)や来年度予算が組まれるスケジュールとなろう。
ガソリン税の暫定税率廃止、医療・介護の公的価格引き上げ、物価高対策を念頭においた地方向けの交付金、自動車税の環境性能割(購入の際にかかる税・車体価格に0〜3%)、赤字企業への賃上げ税制などが挙がっている。
このほか、持論である「危機管理投資」「成長投資」への予算が計上されることになりそうだ。
経済対策については、従来の岸田政権、石破政権下の経済対策との重複部分も多そうである。既に、両政権は「新しい資本主義」を掲げて脱炭素・デジタルなどの重点分野に政府支出を拡大してきており、これに伴う補正予算では多額の赤字国債を発行している。
高市氏も赤字国債の発行を前提に補正予算を組むだろうが、それは旧政権でも同様であり、大きく変わるわけではない。
焦点は規模感。
経済対策を伴う補正予算は2022年度:28.9兆円→2023年度:13.2兆円→2024年度:13.9兆円(いずれも予算合計)。今年度は24年度からは一定の規模拡大がみられるかもしれない。
先に述べたように極端なハト派色を出すことも避けたいことから、昨年補正予算並み〜若干の増加程度のイメージで予測している。従来の主張からすると、内容はサイバーセキュリティ強化やエネルギー政策の転換(再エネ重視から原子力等重視)がより前面に出る可能性がある。
予算編成にあたっては、今後連立のあり方などが今後議論されていく。国民民主党の政策と高市氏の主張は親和性が高く、連携が模索される可能性が高そうだ。
Q.給付付き税額控除はどうなるか?
すでに与党と立憲民主党での協議が行われており、議論は加速するだろう。立憲民主党や国民民主党も前向きであり、実現の確度はこれまでになく高まっている。
高市氏自身も述べている通り、具体的な制度設計は議論中、そのインフラ構築等には時間がかかる。このため、短期的な物価高対策というよりは少し長めの課題になる。
即効性はないが、意義はある。
給付付き税額控除は「負の所得税」とも呼ばれる仕組みであり、減税で家計への還元を行う一方、税額が十分にない低所得者には差額分を給付するものだ。低所得者にも減税の恩恵を生む仕組みであるが、現在の日本にとっては「中間層家計への支援手段」が生まれることの意義が大きい。
ここ数年、家計向け支援策の手段として「住民税非課税世帯」などへの給付がたびたび行われてきた。しかし、低所得者に分類されるのは退職後の高齢者が中心であり、平均的には低所得でも保有資産の多い層を、困窮者と判定して支援することに対して度々批判が生じていた。ストックリッチな家計は流動性制約に直面しておらず、消費喚起策としての効果も限定的となる。
中間層への支援も意識して行われたのが、2024年の定額減税であった。この際、給付付き税額控除のインフラがない中で、低所得者にも恩恵が及ぶように「給付+減税」の仕組みを急造したが、給付世帯と減税世帯との間に対する制度設計などが複雑になり、給付を担う自治体事務の混乱も招いた。
一律給付か住民税非課税世帯への給付か、しかスムーズに行える家計支援策がない、という状況を打破することが給付付き税額控除の大きな意義の一つとなる。
Q.基礎控除引き上げの行方は?
「年収の壁」の引き上げ:所得税制の基礎控除や給与所得控除の引き上げには前向きな姿勢。
すでに、政府の税制調査会でも基礎控除引き上げの物価連動の仕組みは既に議論が進められているが、高市氏が国民民主党の掲げてきた「178万円」の水準を意識した踏み込みを行うかが注目点の一つである。
もう一つの論点が昨年の改正で地方財政への配慮等の理由で引き上げ対象外とされた住民税の基礎控除。昨年の控除引き上げでは住民税が対象外とされており、減税規模や年収の壁対策としての効果が中途半端なものになっている。
現在の税制調査会の議論でも、住民税は主な対象となっていない模様。定率の住民税の基礎控除引き上げは、累進税率の所得税に比べて低中所得者への恩恵が大きい。この点が中間層重視の高市氏の政策理念と合致することもあり、引き上げの対象を住民税に広げるかは再度論点になる可能性が高いとみる。
Q. 賃上げに関連する政策はどうなるか?
高市氏は他候補が賃金の数値目標を掲げる中で、「民間企業が決めること」として数値目標設定からは距離を置いた。代わりに給付付き税額控除の創設などによる家計支援を掲げている。
賃上げを重視していない、というよりはマクロ需給の逼迫環境を保つことで自然に上がっていく、という考えなのだろう。賃金を直接上げる、というよりは給付付き税額控除を通じた手取りの増加を重視している。
政府は直接関与する賃上げのひとつである医療・介護などの公定価格引き上げは、一部を補正予算で前倒し実施することも示した。インフレ定着の中で物価連動の体系も整えるだろう。
小泉進次郎候補なども公的価格のインフレ連動の仕組みには触れていたが、これは既に石破現政権下で6月閣議決定の骨太方針で記載されていた内容である。与党内での反対も生じにくいだろう。
また、石破首相が重視してきた最低賃金の引き上げについては、トーンは弱まる可能性がある。25年度最低賃金は6.3%引き上げで決着したが、正社員賃金の伸び率は2%半ばで乖離が相応に大きくなっている。
石破氏の目標:20年代に1500円までには引き上げ率のさらなる加速が必要。
先に見たように、分配の主眼を現役中間層に置いているほか、賃上げに政府が介入することに必ずしも前向きではない。
Q.円安は進むか?
ハト派的な金融政策スタンスを持つ高市氏の選出で、市場の初期反応は円安・株高である。
ハト派的なマクロ経済政策から円安イメージが先行する高市氏ではあるが、円需給の観点で注目したいのはエネルギー政策。原子力発電や核融合を推進する立場であり、この点は再エネ重視の岸田政権、石破政権から政策転換が図られる可能性が高い。貿易赤字縮小が期待され、円需給の観点では円高要因になると考えられる。
Q.「ワークライフバランス」はどうなるのか?
総裁選出後の演説で「ワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言したことが注目を集めているが、基本的には自身や自民党の議員に向けられたメッセージであり、労働時間規制の見直しなどについて言及しているわけではない。すぐに労働時間規制の緩和等に発展する可能性は低い。
ただし、高市氏に通底している理念として、働く意欲を高めることでそれを成長に繋げたいという点がある。発言が反響を呼んでいることからも明らかなように、一連の働き方改革に対する揺り戻しの動きやその副作用を指摘する世論が一定程度あることも事実である。
例として、非管理職にしか適用されない労働時間規制(労働基準法)は、管理職への労働時間の皺寄せを生んでいる、自分の意思で働きたい人の選択肢を狭めている、などがある。
そのまま規制を働き方改革前に逆戻りさせるようなことはないだろうが、将来的に働き方改革の副作用や労働時間規制のブラッシュアップ(働きたい人は働けるように)の議論が高まる可能性は見ておきたい。
働き方改革が推し進められていたのは、アベノミクス下のディスインフレ期であり、マクロ経済の需給は現在より幾分緩んでいたと考えられる。過去に比べて、人手不足度合いが深まっていると見られる中で、労働時間規制の緩和は供給力拡大の観点でも正当性は得やすい。
※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 星野 卓也