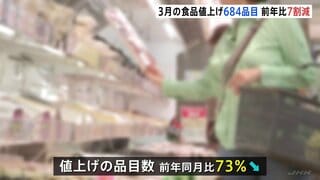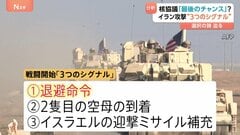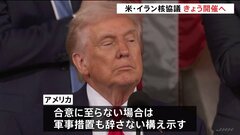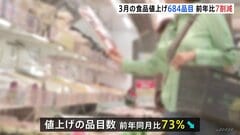「暗黙知」と「人間性」の価値
1) AIが変える仕事の定義
データ分析から明らかになったのは、AIが「競合」するのは、主に若手が担う「定型的で知識ベースのタスク」であり、「競合しない」のは「身体性」「対人関係性」「経験に裏打ちされた暗黙知」が問われる仕事である、という点である。
すなわち、AIは「人間の仕事を奪う」のではなく、「人間の仕事の定義を変える」のである。AIが代替するのは「作業」であり、人間に残され、むしろその価値が高まるのは「判断」と「共感」である。
この構造的な変化は、若手にとって脅威であると同時に、チャンスでもある。
若手がかつて担っていた「教科書通りの作業」はAIに委ねられ、代わりに求められるのは、ベテランがもつ「なぜそうするのか」という背景を理解する力、つまり「暗黙知」であり、そして人間同士の信頼関係を築く「人間性」である。
AIに作業を任せることで、若手はより早い段階から「判断力」や「人間力」を鍛える機会を得ることができる。
2) AI時代の行動指針
では、これからの時代、ビジネスパーソンはどのように振る舞うべきなのだろうか。それは、AIにできることは、すべてAIに任せてしまうことである。
コードを書く、データを集計する、定型的なメールに返信するといった仕事は、AIの方が速く、正確に、そして安価にこなすことができる。人間がこれらの仕事に固執することは、生産性の向上どころか、自らの雇用を失いかねない行為に他ならない。
3) 人間が担うべき二つの価値領域
それでは、人間が担うべき仕事とは何か。それは大きく二つの価値領域に分けられる。
第一に、「暗黙知」を活用する仕事である。
暗黙知とは、教科書には書かれていない、長年の経験と失敗から培われた「コツ」や「勘」、そして「なぜそうするのか」という背景についての深い理解である。
AIは過去のデータから最適解を導き出すことはできるが、全く新しい状況に直面したときの「直感」や、データには表れない「空気感」を読むことはできない。
複雑なプロジェクトを成功に導くマネジメント、クライアントの言葉の裏にある本音を汲み取る営業、チームのモチベーションを高めるリーダーシップ。これらはすべて、人間の暗黙知が発揮される領域である。
第二に、「人間性」を発揮する仕事である。
人間は、単なる効率や論理だけで動く存在ではない。共感、信頼、安心感、喜びといった感情的なつながりこそが、ビジネスを動かす原動力となる。
AIがいくら完璧なプレゼン資料を作成しても、クライアントの心を動かすのは、資料を語る人間の情熱と誠実さである。
AIがいくら正確な診断を下しても、患者の不安を取り除き、希望を与えるのは医師や看護師など医療従事者の優しい言葉と温かい眼差しである。
未来の職場では、AIが処理する「作業」の部分を切り離し、人間がもつ「判断」と「共感」の力を最大限に発揮することが、競争優位の鍵となる。
AIは強力な「道具」であり、「パートナー」だが、決して「目的」ではない。
我々が目指すべきは、AIを駆使して、人間にしかできない「暗黙知」と「人間性」の価値を最大化し、より豊かで、より人間らしい社会を築くことである。それこそが、AIの時代における真の「競争優位」の源泉となるのである。
※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐
※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。