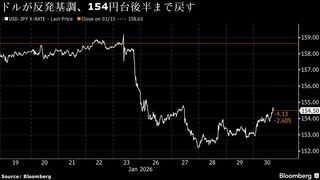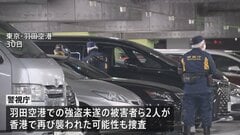(ブルームバーグ):財務省が25日に実施した40年国債入札は、投資家需要の強弱を反映する応札倍率が過去12カ月平均を上回った。市場関係者からは強めの結果だったとの声が出ている。
入札結果によると、応札倍率は2.6倍と、12カ月平均の2.47倍や前回の2.13倍を上回った。最高落札利回りは3.3%と市場予想(3.31%)を下回った。
SMBC日興証券の田未来シニア金利ストラテジストは、応札倍率が高めで、最高落札利回りも市場予想を下回るなど需要がそこそこあり、「強めの結果だった」と語る。利回りの高さに加え、ボラティリティーが低下したことや、財務省が前日の国債市場特別参加者(プライマリーディーラー、PD)会合で超長期債の流動性供給入札の減額を提案したことなど、良い条件が重なったと言う。
今回の入札は、10月4日に予定される自民党の総裁選を前に財政懸念がくすぶる中で行われた。拡張的な財政政策を志向する高市早苗前経済安全保障担当相に対する警戒感が強い一方、小泉進次郎農相の優位も伝えられている。日本銀行の早期利上げ観測で上昇圧力がかかる中長期金利に対し、超長期金利は20年債に続き入札が順調に消化されたことで、上昇に一服感が出ている。
三菱UFJアセットマネジメントの小口正之エグゼクティブ・ファンドマネジャーは40年債入札について「利上げが意識される短いゾーンに比べ割安感もあり、買いやすかったのだろう」と話す。今後も売り圧力が続く中長期債に比べ、超長期債は安定して推移すると予想する。ただ、「日銀の利上げ到達点がはっきりするまで金利が持続的に低下することはないだろう」と述べた。
日銀が国債買い入れを縮小する中、超長期債の主要投資家である生命保険会社は規制対応の需要が一巡し、積極的な投資を控えている。今月3日には新発30年国債利回りが3.285%と1999年の30年債発行開始以降の最高水準を更新。新発20年債利回りも2.69%と99年以来の高水準を付けた。
超長期債の需給悪化と利回り上昇を受けて、財務省は24日に開いたPD会合で10-12月期の流動性供給入札について、残存15.5年超39年未満の超長期債の発行額を減らす案を示した。
(市場関係者のコメントなどを追加して更新します)
--取材協力:グラス美亜.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.