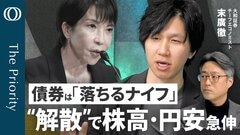「景気減速」「デフレ」「米中対立」「過剰生産」「邦人拘束」…。難しい、怖い、危ない。そんなイメージばかりが先行しがちな中国ですが、実際のところはどうなのか?長らく中国ビジネスに携わり、2023年4月から中国日本商会会長を務める本間哲朗パナソニックホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員・中国北東アジア総代表に中国でビジネスをすることの面白さや今最も注目すべきポイント、さらに日中ビジネスの将来像について語ってもらいました。
前編はカオスだったころの中国からその後の驚異的な発展について。さらに「政経一体」の中国で日本商会が果たす役割についてです。
(前・後編のうち前編。毎週水曜日に配信:JNN北京支局のポッドキャスト「北京発!中国取材の現場から」より抜粋・再構成。8月22日北京市内で収録)
「電気がない上海」「天安門事件」…中国勤務は「ハズレくじ?」
Q初めて中国に来た時の印象はどうでしたか?
本間会長
上海に1989年1月、北京は1991年に初めて来ました。1989年の上海は「真っ暗」でしたね。電力が不足していたので街灯がないんです。車も全然走っていない。タクシーを呼ぶときは外国人の宿泊を受け入れている外国人宿泊所へ行って「外貨兌換券」という外国人専用の特別なお金を使わないと手配できない時代でした。今はアプリでパッとタクシーが呼べちゃうので若い人に話しても信じてくれないんですけれども。本当にこの40年の中国の変化は我々日本人にも中国人にも想像を絶する幅だと思いますね。
この話をすると中国メディアの若手記者も首をひねって信じようとしないんです。「上海の浦東地区の開発は1991年に始まったんだよ。だから私が1989年に上海に行ったときは全く何もない荒れ地だったんだよ」っていうと「そう言われればそうですね」となるんですけれども、そのぐらい激しい発展を成し遂げてきたんですね、この国は。
Q当時は「この国で商売するのか」と不安になりませんでしたか?
本間会長
1985年に入社してその年の秋に「本間さんは台湾に行って中国語を勉強してもらう」と人事部に言われたんですけども「ちょっとハズレくじかな」と思いましたし同期の女性陣からは「本間くん格好わるい」って言われましたですね(笑)。
Qその頃の主流はやはりアメリカだったんですか?
本間会長
アメリカやヨーロッパに行けるのが海外研修生の憧れの的だったんですが同期20人のうち先進国に行けるのは4、5人で他は発展途上国に行くんです。そういう意味ではあまり気にならなかったです。
Q語学研修中の思い出はありますか?
本間会長
当時、中国と台湾は「三不通政策」(貿易・郵便・往来を認めない)をとっていました。同期で中国語を勉強した4人のうち2人が北京、1人が上海、そして私が台北でしたが3人とは2年間全く連絡が取れなかったです。2年経って大陸に行った同期から聞いたのは驚愕の大陸事情で、彼らは北京大学、復旦大学といった一流大学の外国人留学生寮に住んだのですが、食事が相当厳しかったと。白いご飯の中に石や砂が当然のように混じっていたというんです。目方をごまかすためなんですね。
一方の私は台北で毎週末、会社の先輩と一緒にお寿司屋さんへ行ってカウンターで寿司を食べるっていう生活をしていたので、そういう話をしたらたいそう嫌がられましたけども(笑)、80年代末の台北は今とあまり変わらない、非常に日本に近い生活水準でしたので、そういう意味では台湾に行けたのは本当に幸運だったと思いますね。