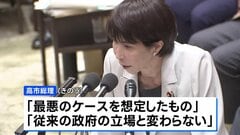(ブルームバーグ):トランプ米大統領は7日、8日付けで退任するクーグラー米連邦準備制度理事会(FRB)理事の後任として、ホワイトハウスのミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長を選んだと明らかにした。
トランプ氏はミラン氏について、「彼は私の政権2期目発足当初から共に歩んできた人物であり、経済の世界における専門性は比類ない。彼は素晴らしい仕事をするだろう」と自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。
ミラン氏が就任するには、上院の承認が必要となるが、トランプ氏はミラン氏がクーグラー理事の残りの任期を務める見通しを示した。任期は来年1月末までとなる。
「その間に、恒久的な後任者を引き続き探していく」と、トランプ氏は指摘した。
ミラン氏の指名が伝わると、ブルームバーグ・ドル・スポット指数はそれまでの上げを消した。連邦準備制度は今のところコメント要請に応じていない。
ハーバード大学で経済学博士号を取得したミラン氏は、金融当局に対するトランプ氏の利下げ要求に同調している。トランプ氏の他の側近の多くに比べて、一段と抑制された口調で自身の見解を述べるミラン氏だが、連邦準備制度を鋭く批判。一部では異端と見なされるようなFRB改革案も提示している。
ミラン氏は、現在財務省で首席補佐官を務めるダン・カッツ氏と共同で執筆した2024年3月の論文で、連邦準備制度改革に向けた24ページの計画を示し、「集団思考」が政策運営上の一連の失策を招いたと指摘した。また、連邦準備制度が本来の権限を逸脱し、政治的な領域にまで踏み込んでいると批判した。
「連邦準備制度の近年の実績を踏まえると、その運営が中央銀行の独立性に関する最善の手法に沿っているか疑問が生じる」と指摘している。
論文ではさらに、連邦準備制度における金融政策と銀行規制・監督の分離を求め、後者に関する権限をFRBから切り離すべきだと主張。この変更には法改正が必要となるが、「金融政策プロセスが不要に損なわれるのを回避できるだろう」と論じていた。
なおミラン氏は、ヘッジファンド会社ハドソン・ベイ・キャピタルのシニアストラテジストだった24年11月の論文で、世界の安全保障や準備通貨ドルといった国際公共財を米国が提供していることに対し、同盟国や貿易相手国・地域による応分の負担分担の構想を提示。ドル安誘導を目指す多国間取り決め「マールアラーゴ合意」のアイデアも示していた。
金融政策への影響
インテグリティ・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジョー・ギルバート氏はミラン氏について、「予想外の人選ではあるが、市場が想定していた枠組みの中には収まっている」と述べた。
その上で、ミラン氏が理事に就任すれば、「FRB内で緩和策を支持する新たな声が加わることになる」と予想。市場は正式に金融緩和サイクルに入ったとの見解を示した。
ただ、ミラン氏が大きな影響を与えることはないとの見方もある。ジョージ・メイソン大学マーカタス・センターで上級研究員を務めるデービッド・ベックワース氏は、「結局のところ、彼は1人の理事に過ぎず、構造的な変化をもたらしたり、大幅な利下げを主導したりすることはないだろう」と分析。「わずか数か月でできることはあまり多くない」と話した。
米経済は徐々に減速しているものの、金融当局は今年これまでのところ利下げを見送っている。トランプ氏の強硬な関税措置がインフレ再燃につながる可能性への懸念が背景にある。最近のデータでは、一部の分野で関税の影響が確認されているが、全体としてはおおむねインフレ圧力は抑制されている。
ミラン氏は7日早い時点のブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、トランプ氏の関税措置について、「マクロ経済的に有意な物価上昇圧力の証拠はゼロだ」と論評。「全体として関税に起因する大幅なインフレは予想していない」とし、関税措置の結果としてインフレが生じたとしても、「それは一時的な物価水準の上昇で、持続的な傾向にはならないだろう」と語った。
上院は現在、8月の休会中で、ワシントンに戻るのは9月初めの予定だ。ミラン氏は現職に就く際に指名承認手続きを経ているため、FRB理事承認プロセスは迅速に進むと考えられる。一方で、共和党指導部が優先事項として扱ったとしても、承認には数週間を要する可能性がある。
上院銀行委員会のスコット委員長(共和)はミラン氏のことを、「優れた経済学者」で、トランプ氏にとって「非常に重要な」アドバイザーと評している。
原題:Trump Names Miran to Fill Seat on Federal Reserve Board (3)(抜粋)
(ミラン氏の過去の論文に関する情報を追加して更新します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.