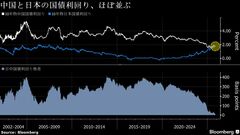(ブルームバーグ):金融庁は30日、銀行の信用リスク管理体制の高度化に向けた検証結果を公表した。融資先における粉飾決算といった会計不正が増加している傾向を踏まえ、銀行側で異常を察知する人材育成が課題だと指摘した。
融資先で長期間にわたる粉飾などが発覚すると、銀行は多額の与信費用を計上することになる。金融庁はできるだけ早期に検知が可能となる体制の整備を促してきた。
「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート」を公表した。資産の架空計上や負債の未計上など検証先の銀行で発覚した粉飾事案の主な手口を記載している。
検証した多くの銀行において、不正を検知する自動アラートシステムなどを導入していたが、実際にはチェック体制が機能していない事例を確認した。
例えば、グループ企業で親会社の信用力を過信した結果として子会社での粉飾が発覚した例があった。
実権者が遠隔地にいる融資先について、定期的な面談を怠っていたが、自行よりも資金量が多い銀行が多額の与信を許容しているために安心して優良先と判断していたところ、粉飾が発覚した事例も見つかった。金融庁は「信用リスク管理態勢の深刻な欠陥」と厳しく批判した。
銀行の営業部門や審査部門など、それぞれの部署が適切に対応していれば、不正についてなんらかの手がかりをつかむことができたケースもあるとみる。
金融庁は「融資規律の弛緩(しかん)が懸念される事案が多数見られる」と指摘した。「金融機関が目先の収益確保を急ぐあまり、健全な猜疑心と職業的懐疑心を失ってはならない」と警鐘を鳴らす。
銀行のリスク管理体制の強化に向け、財務に現れにくい異常や違和感を察知する能力を備えた人材を計画的に育成する必要があると提案した。融資先の状況を確認する項目の見直しなども課題だと指摘した。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.