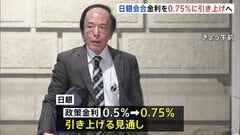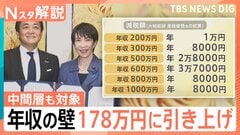「元リフレ派」の安達前日銀審議委員に「リフレ政策」を総括してもらった
今回のインタビューは「日銀の現在地といま取るべき戦略」というテーマで行われた。これまでのリフレ政策について総括することが目的である。なお、リフレ政策という言葉の定義は人によってやや異なる印象だが、当レポートでは強力な金融政策や財政政策によってデフレ状態からインフレ状態になることを目指す政策であるとする。
安達氏はもともとリフレ派と呼ばれる立場から積極的な金融緩和や財政出動によってデフレ脱却を急ぐべきだと主張していた。20年3月に日銀審議委員に就任する前の書籍などによると、財政出動による金利上昇圧力や円高圧力が政策効果を抑制してしまうという考えから(クラウディング・アウト)、積極的に金融緩和をすべきであるという主張だったと記憶している。言い換えれば、開放経済におけるマンデル・フレミングモデルを重視した立場である。少なくとも、マネタリーベース(中央銀行による通貨供給量)を増やせば物価が上がるという「貨幣数量説」を重視したマネタリスト的な視点ではなかった。
今後もリフレ政策が必要になる可能性はあるのか?などを尋ねた
筆者はインタビュアーとして、①利上げを主張するようになった背景は何か、②インフレ率が上がったことは過去のリフレ政策の効果(成功)と考えているのか、③今後もリフレ政策が必要になる可能性はあるのか、という点を中心に尋ねた。
リフレ政策は非常に幅広い概念であり、リフレ派の論者によって重要視する政策パスは異なる。したがって、安達氏の考えがリフレ派の考えを代表するわけではない。とはいえ、リフレ派の代表として日銀審議委員に選ばれたとみられている安達氏によるリフレ政策(異次元緩和)の総括や回顧は重要だろう。
リフレ政策の効果は主張しつつも、実質成長率の弱さは想定外だったという見解
筆者が重視した論点と安達氏の回答に対する解釈については以下である。
①利上げを主張するようになった背景は何か
安達氏は、デフレ状態ではリフレ政策が重要だと考えていたが、すでに日本経済はインフレを警戒する状況になっているため、段階的に利上げを進めることが重要だと主張した。リフレ政策が間違いだったというよりは、もうリフレ政策が役割を終えたと考えているようである。デフレ状態が終わったと判断しているポイントについては、企業がマージンを拡大する動きが拡がり、コストカット体質が変わってきたことを重視しているという。
アベノミクス時に盛んに議論された「リフレ派かどうか」といった最適な経済政策に関する考え方の違い(主張の違い)は、程度問題だったと言うことができる。というのも、日本経済にとってデフレ・スパイラルが課題だったということは共通認識だろう。そして、ある程度は金融緩和によるサポートが必要だ、という点もほとんど反論の余地はなかったと言える 。金融緩和の必要性が広く認識される中で、安達氏はやや強めに主張していただけであると、考えることができる。
いずれにせよ、デフレ状態が終わったと判断して「リフレ政策は役割を終えた」と主張すること自体には一貫性がある。安達氏はリフレ派の考え方を変えて利上げの必要性を主張しているのではなく、一貫した考え方の延長線上で利上げの必要性を主張している。
なお、現在もリフレ政策が必要であると主張している論者もいる。例えば、足元のインフレはコストプッシュによる一時的なものであるものとしてデフレ状態が終わっていないという解釈がある。また、最近のインフレ圧力を抑制するためには供給力を強化する必要があり、そのためには低金利を維持して好景気状態を続けるべきであるという主張もある(高圧経済論)。このような見方に対して安達氏は、否定的だった。
今となっては、何が「リフレ派の主流」だったのかは分からない。しかし、安達氏はインタビューで、「たぶんリフレ派を破門されている」と述べていた。依然としてリフレ政策の必要性を主張する向きからみれば、安達氏の主張は受け入れられないということだろう。アベノミクス時に「十把一絡げ」にされていたリフレ派という存在は、インフレ高進を経て考え方の違いが鮮明になり、もはや一緒くたにできない状況にある。