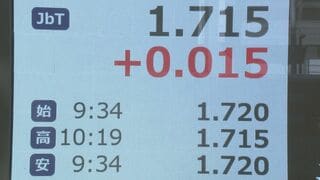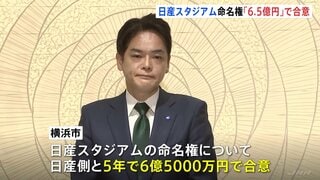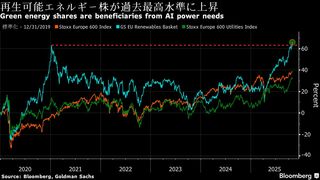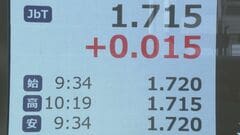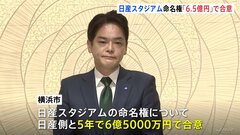(ブルームバーグ):日本株ストラテジストの予想と実際の株価には統計的に「有意義」な結果を見いだせず、投資機会が増えている個人投資家はこうした認識が必要だと野村証券出身で東京理科大学大学院の田村浩道教授が指摘した。
証券会社のストラテジストによる年末時点のブルームバーグ・コンセンサス予想(12カ月先)と実際の株価を2004年末から20年間にわたり田村教授が日経平均株価で比較した。結果として予想と実績の相関関係はわずかに逆になることを示す「マイナス0.2」という係数が得られた。さらにストラテジストの株価予想は上昇に偏る傾向もあった。
日本政府は新しい少額投資非課税制度(NISA)導入や個人型確定拠出年金(iDeCo)を含めて資産運用を後押ししており、投資戦略需要が個人投資家を含めて増す中、市場のプロでも株価予想は容易でないことが浮き彫りになった。専門家予想と実績がかい離するリスクを認識する重要性を示している。
田村教授はブルームバーグの取材で、従来はストラテジストと機関投資家というプロ同士の「あうんの呼吸」で予想が取り扱われ、この問題が深刻化しなかったと指摘。今後は個人に誤解されないために「予想数字は当たりづらいことをまず分かってもらった上で、予想の背景について理解してもらうことが望ましい」と語った。
統計学では一般的に相関係数がプラス1.0は「完全相関」、プラス1.0-0.7は「強い相関がある」、0.7-0.4は「相関がある」、0.4-0.2は「弱い相関がある」、0.2-0.0は「ほとんど相関がない」とされる。
ストラテジスト予想が上昇に偏る傾向について田村氏は、証券業界は顧客の資産が長期的に増加したか、純増したかが重要だと言及。純増には、将来的に資産が上がると主張しなければ資金が入りづらいとして「会社の方向性と弱い忖度(そんたく)がある、いわゆるセルサイドバイアスということだ」と分析する。
予想と逆
運用会社でファンドマネジャーの経験がある岡三証券の松本史雄チーフストラテジストは、運用会社時代は「ストラテジストが強気、弱気ということよりも、その背景にあるロジックを重視していた」と話す。その上で、ストラテジストとして重要なのは「前提条件やトレンド変調の際にいち早く知らせることだ」とみる。
田村教授が分析した20回のうち予想リターンがプラスだったのは17回で、実際は6回がマイナスだった。マイナス予想は3回で、アベノミクス相場時のように急激に株価が上がり、予想修正が追いつかなかったケースが目立ったという。「ストラテジストの強気、弱気と市場の結果は若干逆の関係にあった」と述べた。

さらに今後証券会社がストラテジスト予想を取り入れた投資助言サービスを個人にまで普及させると、個人のポートフォリオ形成にも予想が影響を与えかねないと指摘。予想が当たらない結果となれば「資産運用の流れが止まるかもしれず、注意が必要だ」と危惧した。
田村氏は早稲田大学理工学研究科を経て1991年に野村総合研究所入社、93年に野村証券クオンツアナリスト、ロンドンでのチーフクオンツストラテジストなどを経て04年にエクイティクオンツリサーチ部長、12年にチーフストラテジスト(日本株)、17年にクオンツリサーチ部長。18年にFTSEラッセルHead of Investment Research, APAC、22年から東京理科大学大学院(経営学研究科技術経営専攻)教授。
(6段落に予想が上昇に偏る要因などを追加して更新します)
--取材協力:山﨑朝子.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.