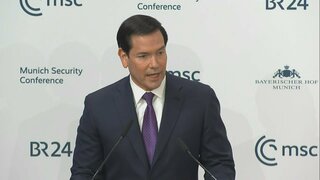このところの中国経済を巡っては、深刻化する不動産不況が幅広い経済活動の足かせとなるとともに、若年層を中心とする雇用不安に加え、逆資産効果の影響も重なる形で家計消費をはじめとする内需は力強さを欠く推移をみせている。他方、中国国内の過剰生産能力はいわゆる『デフレの輸出』を招くことが警戒されるなか、欧米など主要国のみならず、新興国の間にも中国製品に対する追加関税を課す動きが広がりをみせるなど、外需を取り巻く環境も厳しさを増している。
当局は不動産不況の元凶となってきた在庫解消を目的とする施策のほか、中国人民銀行(中銀)も需要喚起を目的とする住宅ローン金利の引き下げや頭金規制の緩和に加え、最大1兆元規模の貸付制度の創設に動いた。さらに、7月の3中全会(第20期中央委員会第3回全体会議)直後には全面的な金融緩和に動くなどの対応を強化させた。
しかし、一連の対策公表にも拘らず、その後も不動産需要は回復せず、市況も下げ止まりの兆しがみられない展開が続くとともに、内需は下振れするなど一段の景気減速が意識される展開が続いてきた。
こうしたなか、先月24日に中銀の潘功勝行長と国家金融監督管理局の李雲澤局長、証券監督管理委員会の呉慶委員長の3人が合同で記者会見を行い、預金準備率と7日物リバースレポ金利の引き下げに加え、既存の住宅ローン金利の引き下げ、住宅ローンの頭金規制緩和、株価下支え策などに動く方針を明らかにした。
さらに、共産党は中央政治局会議を開催するとともに、一連の金融緩和策のほか、財政出動を含めた総合的な対策を通じて今年の経済成長率目標(5%前後)の実現を後押しする方針が決定された模様である。なお、金融市場においては当局が公表した株価下支え策を好感する形で主要株価指数が大幅に底入れするとともに、一時的に2022年12月以来となる水準を回復するなど活況を呈する動きをみせている。
他方、12日に記者会見を行った藍仏安財政部長は、特別国債の大幅な発行増を通じて低所得者層に対する補助金支給、不動産市場支援、国有銀行の資本拡充を図ることで景気回復を後押しする方針を明らかにした。なお、一連の発言においては年内の債務割当額や未使用資金を含めた形での支出可能な額が2.3兆元(GDP比1.83%)あるとする一方、具体的な支援策の規模には言及せず、どのような形で実施されるかは不透明なところが多い。