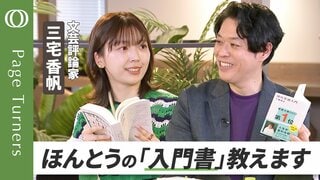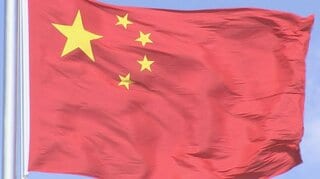金融引き締めからの転換を中心とした「3重の政策転換」の必要性
ピエール・オリビエ・グランシャ氏は「インフレが後退する中、世界経済には3重の政策転換が必要」とし、①金融引き締めの転換、②財政政策の健全化方向への転換、③成長を促進する構造改革、を挙げた。②財政健全化と③構造改革についてはお決まりの内容と言えるが、①金融引き締めの転換については、重要だろう。引き続き、インフレ圧力の再燃には注意が必要とされたが、「主要中央銀行が金融緩和を進める道が開けている」と記された。インプリケーションとしては、FRBの利下げ傾向が続く可能性が高いこと、日本の利上げサイクルは長続きしない可能性が高いこと、などが挙げられる。
過去のインフレ高進は「一時的要因」という結論に
IMFはブログで「世界的なインフレが金融政策にもたらす教訓」について分析し、「当初、パンデミックに伴うロックダウンによって、需要がサービスから財へとシフトした。しかし、それと同時に過去に例を見ない財政・金融刺激策によって需要が喚起され、多くの企業は十分に早く生産を拡大できなかったため、供給と需要のミスマッチが生じ、一部の部門では価格が上昇した」と結論付けた。すなわち、インフレ高進は一時的な現象である、というものである。IMFは以前よりこのようなスタンスだが、改めてインフレ率や中立金利が長期的に高止まりする見方とは距離をとった格好である。市場ではすぐに「構造変化」であるとか、「This time is different」という主張が聞かれるが、その多くが聞こえのいいナラティブか、中央銀行が市場の期待をコントロールしようという意図で用いているナラティブだろう。IMFのような冷静な視点が肝要だと、筆者は考えている。
(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)