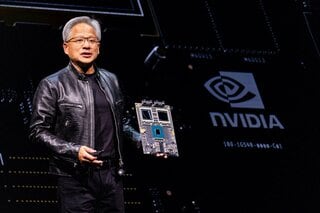衆院選後の政局
10月27日の衆院選では、与党の自民、公明両党が大きく議席を減らし215議席となり、過半数(233)を18議席割り込んだ。ただ、最大野党である立憲民主党が大幅に議席を増やしたとはいえ148議席にとどまる中、考え方が大きく異なる野党が結集して、「非自公」政権を構築するのは(可能性ゼロとまではいわないまでも)非常に難しい。自公と他党(国民民主党、日本維新の会など)の連立・閣外協力ないしパーシャル連合がメインケースとして想定される。
政治資金規正強化、財政拡張、利上げはゆっくり
自公を軸とする政権が続く場合、石破首相は協力を求める政党の政策を取り入れることを明言している。したがって、連立、パーシャル連合いずれの形になるにしても、政策の方向性は、①政治資金規正の更なる強化、②家計向けを中心とする財政拡張(教育無償化、家計補助、景気対策拡大、「年収の壁」の引き上げなど)、③賃上げ、金融資本市場の安定が続けば日銀の段階的な利上げは可能だが、野党各党の主張などから考えて、慎重なペースで行われるという3点に整理できよう。
民間主導の改善
アベノミクスが始まった2013年当時は、企業の利益率がまだ低く、賃金・設備投資の抑制が続いていたため、政策によって経済を刺激することが非常に重要だったとみる。しかし、昨年来の日本の名目成長率の加速と株価の上昇は、利益率が十分に回復し民間のダウンサイジングが終了したことや、グローバルなインフレ環境・為替レンジの変化がドライバーになっているとみる。実際、大企業の売上高経常利益率(財務省法人企業統計ベース)は過去最高水準へ回復、GDPに占める設備投資の比率はデフレ・ゼロインフレ期であった過去レンジを上抜けてきた。
日本の政局の不安定化(パーシャル連合などの場合)が企業心理に与える影響や財政規律の緩みに対する金融市場の反応には注意が必要とみるが、経済政策が景気をサポートする中、国内要因からみれば、日本経済は賃上げの進展など民間主導の改善が継続可能な状況にあるとみる。
足元の米国は安定
米国については、労働生産性の上昇が続き、企業収益、雇用者所得、インフレのいずれも良好な環境にあるとみる。単月の雇用統計は特殊要因などで変動が激しいが、3カ月移動平均で月間10~15万人の雇用増ペースが維持できれば、景気失速リスクは低いだろう。