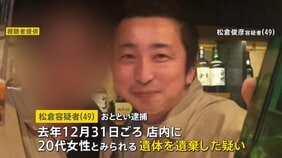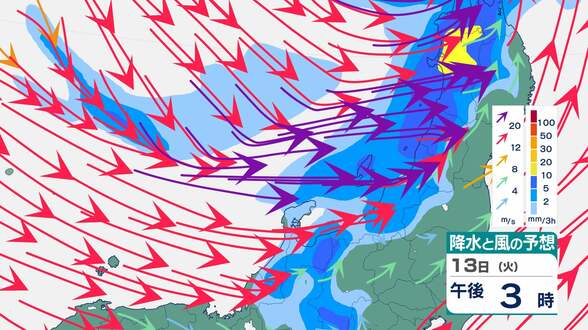原子力規制委員会は13日から2日間の日程で石川県志賀町にある北陸電力・志賀原子力発電所の断層の現地調査を始めました。原発の再稼働を目指す北陸電力にとって、長年続く断層の審査が山場を迎えています。
記者:
「こちらは、原発に最も近い活断層、福浦断層です。現在、形状の確認が行われています」
この現地調査は志賀原発2号機の再稼働に向けた安全審査の一環で、原子力規制委員会の石渡明委員や規制庁の職員が、原発の敷地内やその周辺の断層を調査します。
初日は原発の東側およそ1キロに位置する「福浦断層」の断層面を確認し、その形状や全体の距離を確認しました。
志賀原発2号機をめぐっては2014年に安全審査を申請。2016年に規制委員会の有識者調査団が、敷地内の一部の断層について活断層の可能性があるとの評価書をまとめました。
国の新たなルールでは原発の重要施設を活断層の上に設置することはできません。志賀原発の敷地内断層の活動性を焦点に、安全審査の会合で6年にわたり議論が続いています。
北陸電力:
「断層の位置はこちら、この赤色のピンが打ってある位置になります。この断層は福浦断層西側に対応する断層と評価をしています」
今回の現地調査は、去年11月に続き2回目です。調査した「福浦断層」は原発に最も近い活断層で、断層の距離などが志賀原発の耐震設計などに影響を及ぼします。
北陸電力は「福浦断層」の距離を3.2キロと見ていて、石渡委員らは「福浦断層」の南側で断層の走りを調査しながら、南の端がどこになるのかを確認していました。
初日の調査を終えた石渡委員は。
原子力規制委員会 石渡 明委員:
「大体あの(福浦断層の)南の端がここであろうということについてはかなり詰まってきました。ただ、なかなかここには断層がありませんという証拠になる地質学的な記述が十分でなくて、それについては今後、審査会合の場できちんと資料を出してもらって、そこで最終的な判断をしたいと思っています」
現地調査は、14日は原発敷地内の断層を調査するほか、北陸電力が新たに提出した断層の薄片試料を確認します。
全国のトップニュース
【速報】日経平均株価 一時1800円以上値上がり 初めて5万3000円の大台を突破 衆院解散報道受け

【速報】イランと取引のある国からの輸入品に25%の「二次関税」 トランプ大統領が「即時発効」と表明 イランへの経済的圧力を強化

きょう日韓首脳会談 シャトル外交の一環 トランプ政権や中国含む地域情勢などへの対応めぐり連携確認へ

トランプ大統領 ノーベル平和賞のマチャド氏と15日に会談へ ベネズエラ情勢について協議

「今度はもっと良い仕事をしていきたい」 “ホテル密会”問題の小川晶氏が再選 前橋市長選挙

トランプ政権 “過去最多”10万件超のビザを取り消し 2024年の2.5倍

米ミネソタ州がトランプ政権を提訴 イリノイ州も

遺体を“店内の壁”に隠したまま新年の営業していたか…北海道・バー経営の松倉俊彦容疑者 店を訪れた人が感じた異変「空気清浄機が何台も」