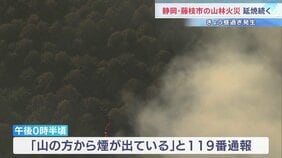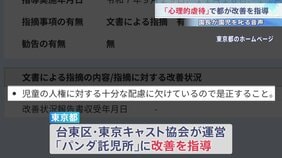長野県の塩尻市北小野と辰野町小野の隣り合う地域で、3日から「小野御柱(おのおんばしら)」の「里曳き祭(さとびきさい)」が始まりました。
祭りの後継者不足が叫ばれる中、伝統を受け継いでいこうと若者が活躍していました。

3日、塩尻市北小野の上田地区から3日間の日程で始まった「里曳き祭」。

長さおよそ18メートル、直径70センチのアカマツが、1キロ離れた小野神社を目指します。

(氏子は…)
「最高に盛り上がってます」
「(何回目の御柱ですか?)6×7=42、7×7=49で…10回くらいだね」

上田地区が担当する「一之柱(いちのはしら)」は、境内に建てる4本の中でも最も大きく、重い御柱です。

威勢よく綱を引っ張る黄色い衣装の男たちの周りに青い法被の氏子たちが…
(青い法被の氏子)「おら方は明日の担当になります。『二之柱』の方の。今日は上田区のお手伝いということで」
(上田地区の氏子)「応援に来ていただいた」
(青い法被の氏子)「明日はまたこっちの衆が応援に来てくれるもんで」

柱を動かすには大勢の力が必要なだけに、担い手不足は深刻です。

上田地区の人口はおよそ250人、15年間で3割も減少しました。

高齢化率も50%を超え、塩尻市にある66の行政区の中でも5番目に高い数字です。
(塩尻市上田区長・赤羽忍さん)
「昔に比べると人数的には半分下ですね。年数重ねるごとにやる人間も年数を重ねて高齢化が進んでですね、将来がちょっと不安はあります」
伝統を守り継ごうと立ち上がったのが地元の若者グループ「青年社(せいねんしゃ)」です。

高校生もメンバーに入って木遣りや踊りを披露するなど、団結して祭りを盛り上げます。

(青年社社長・東原和哉さん)
「どんどんとこの若い世代今の中学校とか小学校の子たちに、次の7年後の御柱で、こういうふうにやっていただければ本当にいいと思ってます。」

上田地区が曳く「一之柱」はお昼頃、小野神社に到着。

御柱の先端を整える「冠落とし(かんむりおとし)」を行います。

この時に出た木のくず=木っ端(こっぱ)は待ち構えていた氏子や観光客に配られました。
これをどうするのか、あとをついていくと…社務所の入り口に行列が。
中では、神職が木っ端に「御柱大祭」と筆書きして御朱印を押していました。

(御朱印をもらった氏子)
「これ玄関に飾ります」
「お守りに。6年後までとっておいて、またここへ来たときにお返しする」

境内では、いよいよクライマックスの建て御柱(たておんばしら)です。
青年社リーダーの東原(ひがしはら)さんを先頭に、氏子たちを乗せた御柱が、ゆっくりと天を目指して立ち上がっていきます。

境内は、フィナーレを見届けようという氏子や観光客で埋まり、熱気に包まれました。

若い力が伝統を受け継ぐ小野神社の御柱祭。

祭りは5日まで行われ、隣の矢彦(やひこ)神社と合わせて8本の御柱が境内に建てられます。