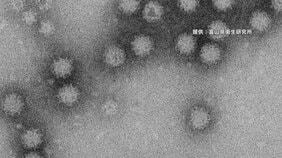飯田市の遠山郷で、800年にわたって続いている霜月祭りが始まりました。
神を迎えて夜通し行われてきた祭りですが、人口減少の中で時間短縮をして受け継ごうとされています。
かつては旧暦の霜月に行われていた霜月祭り。
南信濃地区の熊野神社。
7日の夜、神殿の中には、かまどを取り囲むように観光客などが大勢訪れました。
かまどに湯をたぎらせ祭りの始まりです。
「地元の中学生と高校生の皆様によります学童の舞を奉納させていただきます」
神様に奉納する襷(たすき)の舞。

霜月祭りは遠山郷(とおやまごう)と呼ばれるかつての南信濃村と上村、現在の飯田市に800年以上にわたって受け継がれ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
人口の減少で、担い手不足が深刻となる中、地元の子どもたちに祭りを経験してもらうようになりました。
参加した子ども:
「暑かったっす。大勢の人の前でやったので、すごく緊張しました。楽しいですね」
そして、神様を迎えるためにお湯を沸かす「湯立て」の神事にも参加。
子どもたちは、1か月かけて練習してきたといいます。
参加した子ども:
「1か月ぐらい練習してきて、それが失敗をせずに成功できてよかったです」

熊野神社の霜月祭りは、かつて開催日が決まっていましたが、今では、第一土曜日に変更し、夜通し行ってきた時間も夜9時までとしています。
神と民がふれあう霜月祭り。
熱湯を素手で払う「湯切り(ゆきり)」をきっかけに、神様の面(めん)=「面(おもて)」が次々と登場します。
クライマックスは、「四面(よおもて)」の神様。
「よーせー」

社殿の中を所狭しと飛び回り、氏子や見に来た人の人垣に飛び込んでいきます。
かまどの火に勢いを与えると言われます。
そして!
湯切りで湯を飛ばして、五穀豊穣や生命力を集まった人たちに授けます。
登場した神様の面(おもて)は37。
地元の子どもたちも「面」をつけて、参拝した人たちの中に入っていきます。
南信濃では、地元の若手有志などが祭りをサポートして、伝統を受け継ごうとしています。
氏子代表 平澤一也さん:
「時代に合わせたやり方に変えていくっていうことが大事かなと思いますけど、このやり方でやっていけば絶対ずっと残ると僕は確信をしています」
今年の霜月祭りは残り6つの神社で21日まで行われます。