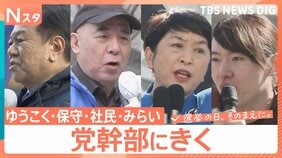特集は、災害時の「水」について考えます。
元日に発生した能登半島地震から4か月余りがたちましたが、被災地では未だ3,000戸以上で断水が続いています。
こうした中、改めて注目されているのが「井戸」の活用です。
長野県内でも起こるかもしれない大地震に対して、できる備えとは。
元日の能登半島を襲った、大地震。

最大震度7の揺れにより、能登地方の広範囲で水道管が破損し、石川県内ではおよそ6万7,000戸が断水しました。
各地から給水車が派遣されるなどしましたが、断水は長期化。
被災した住民(発災3か月):
「いま一番水が欲しいですね。洗濯もしなきゃいけないし」
被災した住民(発災3か月):
「水が一番、大切ですね。電気が来ていても炊事洗濯できん」
洗濯や風呂、トイレなどで使う「生活用水」の不足が深刻な課題となりました。
こうした中、有用性が注目されたのが「井戸水」です。
七尾市では、営業を休止していた銭湯が、近所の人に井戸水を提供。
利用した住民(1月):
「つくづく水のありがたさがわかりました」
水道の復旧のめどが立たない中、珠洲市では新たに井戸を掘った高齢者施設もあったといいます。
災害時の生活を助ける、井戸。
その特徴について、専門業者は…
サクセン 高橋作夫(たかはし・さくお)社長:
「地層が揺れるので、一時的に井戸が濁ったりとか、そういうことはしますけれども、ほとんど被害はない。最初は濁るかもしれないが、すぐ使えると思う」

井戸の掘削業者でつくる「全国さく井(さくせい)協会」の調査では、東日本大震災で94パーセント、熊本地震では97パーセント余りの井戸が、地震後も使用できたといい、「揺れに強い」とされます。
松本市の掘削業者・サクセンの高橋社長は、地区によっては、防災用の井戸の整備も必要になってくると指摘します。
サクセン 高橋作夫社長:
「水が一番困るっていうことが、能登の大震災でもはっきりしたと思うんで、(山間部など)孤立しそうな地域で、きちんと避難所を選定して、井戸も備える。地区ごとに年1回は避難訓練をしますと。そのときに合わせて災害用の井戸がきちんと動くかどうか点検するとか、そういうことは大事だと思います」
災害時に井戸を活用するための取り組みは、県内でも進められています。